�{�e�́u���q�͎�������ʐM�vNo.287�i1998�N4���j�Ɍf�ڂ��ꂽ.
�`�F���m�u�C���������̏�����Ǝ҂̌��N��ԂɊւ����
�@�`�F���m�u�C�����̂̌�n����Ƃɏ]�������l�X�i�����郊�N�r�_�[�g���j�̌��N��ԂɊւ��鋻���[��������肵���̂ŏЉ�Ă��������B�u�����U���B���n�r���e�[�V�����Z���^�[�ł̒����ώ@�f�[�^�Ɋ�Â��`�F���m�u�C���������̏�����Ǝ҂̔픘�e���Ƃ��̑�̂��߂̊����v�Ƒ肷�邻�̕��́A���V�A�̃����U���B�i���X�N���̓쐼��200km�A�l��130���l�j�ɋ��Z���Ă��郊�N�r�_�[�g���̌��N��Ԃ��A�B���ǂƐ���������������������1995�N�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���i�S��34�y�[�W�j�B�����ΏێҐ���1886�l�ƁA60������80���l�Ƃ����Ă��郊�N�r�_�[�g���S�̂��炷��킸���ł��邪�A�Ώێ҂����Ȃ����A�t�ɂ������肵���f�[�^��������Ă���B
�����Ώ�
�@�`�F���m�u�C�����̈ȑO���烊���U���B�ɋ��Z���A�`�F���m�u�C�����̏����ɏ]����A�Ăу����U���B�ɖ߂��Ă����j�����N�r�_�[�g���������̑ΏۂŁA�Ώۊ��Ԃ�1986�N����1993�N�i�ꕔ1994�N�j�ł���B���X���ː��ɑ���m���������Ă������Ɓi���q�͊֘A�Z�p�҂��҂��w���Ă���Ǝv����j�͒����ΏۊO�Ƃ���Ă���B�����Ώێ҂��`�F���m�u�C���Ŏ��̏����Ɍg��邱�ƂɂȂ������������́A�`������40���A�\�����̏��W52���A�u��҂W���ɂȂ��Ă���B�\�P�ɁA�Ώێ҂̍�Ǝ��̔N��A��Ƃ̎����A�L�^���ꂽ�픘���ʂ������B��Ǝ��N���18����40��92���ŁA�����铭��������̔N���ł���B��Ǝ�����1986�N��1987�N�����킹��91.2���Ƒ啔�����\�����A1986�N��1987�N�͂قړ����ł���B1986�N4�`6���ɍ�Ƃɏ]������96�l�́A���ꂩ��Љ��f�[�^�̒��œ��ɒ��ڂ����O���[�v�ł���B�픘���ʂ̋L�^�́A�ǂ��܂ł��ĂɂȂ邩�͕ʂƂ��āA�Ώێ҂̖�R���̂Q�ɓ����Ă���B�������O���픘�̋L�^�����ł���A�����픘�ɂ��Ă͉��̃f�[�^���Ȃ��B��Ǝ����ʂ̕��ϔ픘���ʂ́A���R�̂��ƂȂ���A1986�N�̍�Ǝ҂��ł��傫��203�~���V�[�x���g�ł���B�O���픘�S�̂̕��z�ł́A500�~���V�[�x���g�ȏ�̂X���i0.7%�j�����ڂ���A�Ȃ��ł��P�V�[�x���g�ȏ�R���̕��ϐ��ʂ�1.883�V�[�x���g�ƁA�}���̕��ː���Q���\���ɍl��������ʂł���B
|
|
|||||||||
| �@��Ǝ��N��̕��z�F | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| �@��Ǝ����̕��z�F | |||||||||
| �@ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | ||||
|
|
|
|
|
�@ | �@ | ||||
| �����F
���ʋL�^���� |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
| �@�픘���ʂ̕��z�F | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
| #21�͏d�Ȃ��Ă��邪�����̂܂܁D
*���̂���96�l(5.1%)��1986�N4�`6���ɍ�Ƃɏ]���D **���a��Q�҂ƂȂ����l�X�i�\�S�j�̍�Ǝ����ϔN��̒l�D |
|||||||||
��������
�@��Ɠ����̈�ËL�^�ɂ��ƁA�P���݁A����A�f���C�A�q�f�A�S���ɂƂ��������N�����̏Ǐ�1986-87�N�̃��N�r�_�[�g����84�`88���ɋL�^����Ă����A�ƕ��͏q�ׂĂ���B���ɋ����[���L�q�ł��邪�A�c�O�Ȃ��炻�̋L�^�ɂ��Ă̏ڂ����L�q�͂Ȃ��B
���S���F�\�Q�����悤��1986�N����1993�N�ɂ����Ă̂W�N�Ԃ̎��S�҂�87�l�ł������B��Ǝ����ʂɎ��S�����ׂ�ƁA86�N��Ǝ҂̒l���傫�����ƁA�܂�91�N���玀�S���}�����Ă��邱�Ƃ̂Q�������ɒ��ڂ����B86�N��Ǝ�856�l����W�N�Ԃ�55�l�i��16�l�ɂP�l�j�Ƃ������S�́A�����̍�Ǝ����ϔN�30��O���ł��������Ƃ��l����ƒ����I�ɂ����Ȃ�̑傫���ł���B�N��\���Ȃǂقړ����̏W�c�ōl������A86�N��Ǝ҂�87�N��Ǝ҂̎��S�����ׂ�ƁA86�N��Ǝ҂̕�����Q�{�ł���B���̂��Ƃ́A86�N��Ǝ҂̔픘���ʂ̑傫�����Ƃ����S�̑����ƊW���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B�����ɂ��ẮA�@���́E���ŁE���E�i39.4���j�A�A�z��n�����A�B�����s���A�C�����V�����A�Əq�ׂ��Ă��邪�A�c�O�Ȃ���ׂ����f�[�^�͎�����Ă��Ȃ��B
�@�����W�c�S�̗̂ݐώ��S����10���l����4613�l�ŁA�����U���B�̓��N��j�����ς�7116�l�ɔ�����Ȓl�ł���B�������A���N�r�_�[�g���͌��X���N�Ȑl�X�ł��������ƁA�N��\���̈قȂ�W�c�̔�r���@���͂����莦����Ă��Ȃ��i���Ȃ�G�Ȕ�r�Ǝv����j�Ƃ�������肪����̂ŁA�ȍ~�̃f�[�^���܂߁A�B���ςƔ�r����c�_�ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B
�K���������F�\�R�̓K�������Ɋւ��钲���f�[�^�ł���B�W�N�Ԃ̗ݐσK����������1000�l����14.9���ł��邪�A1986�N��Ǝ҂ł�18.7���ł���A��Ǝ����ƃK���������Ƃ̑������F�߂���B�Ȃ��ł�1986�N4�`6����Ǝ�96�l����͂V���i��14�l�ɂP�l�j�̃K�����������Ă���A���̃O���[�v�̃��X�N���ɂ߂đ傫�����Ƃ������Ă���B���ʕʂ̔������ł́A�b��B�K���A�]��ᇁA��̃K���Ƃ�������r�I�܂�ȃK���̔������F�߂���B
�@�������̓��N��j���̏B���σK����������1000�l����24.2���ƁA���N�r�_�[�g�����傫�����A���S���̏ꍇ�ȏ�ɁA��r�̑Ó����̖�肪�c��B
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ | ||||||||||
|
|
�@ |
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||||||||||
| *10���l����D**���N��j���̏B���ρD | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ | �@ | �@ |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ | |||||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | �@ |
|
�@ | �@ |
|
|||||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
�@ |
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||||||||||
| *1000�l���� | |||||||||||||||||||||
���a��Q�ҁF�\�S�́A���a��Q�҂ƔF�肳�ꂽ���̐��ڂ������Ă���B���a��Q�҂Ƃ́A�g�̏�Q��a��̂��ߒʏ�̘J���ɏ]���ł��Ȃ��ƔF�肳�ꂽ�l�X�ŁA�Ǐ�̏d�Ăȏ��ɑ�T�x�����V�x�ɕ��ނ���A���x�ɉ������Љ�ۏ�̑Ώێ҂ƂȂ�B1886�l�̃��N�r�_�[�g���̂���1993�N�܂ł̔F��҂�454���i��T�x�Q���A��U�x327���A��V�x125���j�ŁA�����Ώۂ�24.1���ɒB���Ă���B�Ή�����B���ς̎��a��Q�җ��ɔ�ז�S�{�̐����ł���B
���S��K���̏ꍇ�Ɠ������A�F��҂̊����ƍ�Ǝ����ƊԂɋɂ߂Č����ȑ��֊W���F�߂���B���a��Q���͍�Ǝ����������قǑ傫���A�Ƃ�킯�A1986�N4-6����Ǝ҂̒l��93.8���ƁA�قڑS�������a��Q�҂Ƃ�����قǂ̐����ł���B1991�N����F��Ґ����}�����n�߂Ă��邱�Ƃ́A���S���̏ꍇ�Ɠ����X���ł���A���S���A�K���������A���a��Q���ɋ��ʂ̗v�����֗^���Ă��邱�ƁA�܂莖�̏�����Ǝ��̔픘�̌��ǂƂ��Ă����̉e���������Ă��邱�Ƃ��M�킹��B
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ |
|
�@ |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
�@ |
|
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||||||
| *1000�l���� | |||||||||||||||||
�\�T�͔ނ�̎��a�̓���ł���B�z��n�����i��������S���a�j���P�ʂł���͈̂�ʓI�Ƃ��Ă��A�����_�o�n������_�a�̑������Ƃ����ڂ����ł��낤�i���ҍ��킹��46���A�B���ς̏ꍇ�͍��킹��9.4���j�B
|
|
||
|
|
|
|
| �z��n |
151
|
34.5
|
| �����_�o�n |
108
|
24.7
|
| ���_�a |
95
|
21.7
|
| �����V���� |
27
|
6.2
|
| �ݒ�� |
13
|
3.0
|
| �t������ |
12
|
2.7
|
| �ҒŊߎ��� |
12
|
2.7
|
| ������n |
7
|
1.6
|
| �O�������� |
6
|
1.4
|
| �����̎��� |
4
|
0.9
|
| �C�ǎx�� |
3
|
0.7
|
| ���v |
438
|
�@ |
���̑��̉e���F�����Ώۂ̂���1068�l�̍b��B�ׂ��������ʂł́A�b��B���A�b��B��ȂǂƂ������Ǐ�601�l�i56���j�ɔF�߂��A�L�Ǘ��͏B���ς�1.7�{�ł������B���̂����A�b��B��A���ȖƉu�b��B���A�b��B���ŏǂƂ������d���b��B�����i59�l�j�̗L�Ǘ��͏B���ς̖�10�{�ł������B
�@1987�N����1994�N�ɂ����Ē����Ώێ҂���171�l�̎q�������܂�Ă���B�q��������N��w�i18�`35�j�ł̂W�N�Ԃ̏o�����i�P�l����0.22�l�j�́A�B���ς̂R���̂P�ł������B
�R�����g
�@���N�r�_�[�g���̌��N��Ԃ��������Ă���Ƃ����b�́A�}�X�R�~�A�̌��k�A�f�ГI�f�[�^�Ȃǂł����Ԃ�O���猾���Ă���B�܂��A�E�N���C�i�A�x�����[�V�A���V�A�̃`�F���m�u�C����ЂR�����ł́A���N�r�_�[�g�����܂ߔ�Ў҂̍��Ɠo�^���x������ǐՒ������s���A���X�ɂł͂��邪�f�[�^���������B
�@�����������E�f�[�^�̒��ŁA�M�҂��ł����ڂ��Ă����̂́A���N�r�_�[�g���̎��a��Q�җ����ߔN�}�㏸���Ă������Ƃł������B�}�P�́A������肵���f�[�^���A����܂ł̃f�[�^�ƍ��킹�Ď��������̂ł���B������̃f�[�^�ɂ����Ă�1990�N�����玾�a��Q�җ��̋}���ȑ������F�߂���B����̕��̃|�C���g�́A�}�P�̂悤�ȌX�����A���S����K���������ɂ��F�߂��Ă��邱�Ƃł���B����܂ł̃f�[�^�̌���ł́A���a��Q�҂̑����́A�F�肳��ĎЉ�ۏ���邽�߂́u�������̑����v�ł���Ƃ��A�u���˔\���|�ǁv��A���R�[���т���̂����ł���A�Ƃ������������\�ł������B����̃f�[�^�́A���S���A�K���������A���a��Q�җ��ɋ��ʂ���v�������邱�Ƃ������Ă���A���̗v���Ƃ��đ��ɍl������̂����̏�����ƂɂƂ��Ȃ��픘�ł���B
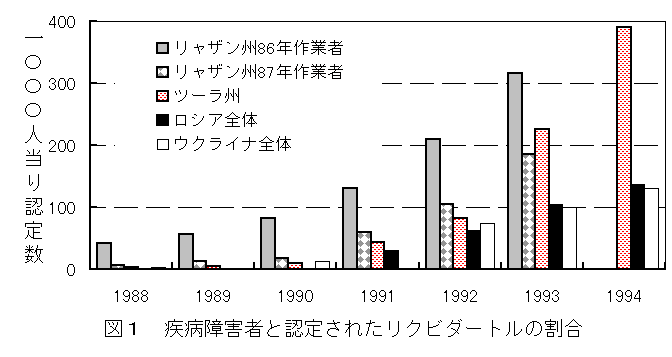
���F�����U���B�͕\�S�̃f�[�^�A�c�[���B�i���V�A�j�́ADelgado�i1998�j����V�A�S�̂̃f�[�^��Ivanov�i1996�j��E�N���C�i�̃f�[�^��Buzunov�i1996�j�ɂ��D�e�o�T�͍�����KURRI-KR-21���Q�Ƃ��ꂽ���D
�@IAEA�Ȃǂ���Â���1996�N�S���ɊJ���ꂽ�u�`�F���m�u�C��10�N������c�v�́A���N�r�_�[�g���͒��ڂ��ׂ��W�c�ł͂��邪�A�����a���܂ߔނ�̊Ԃɔ픘�̉e���͔F�߂��Ȃ��A�ƌ��_���Ă���B���̂T�N�O�AIAEA���J�������ۃ`�F���m�u�C���v���W�F�N�g��c�ɂ��Ďw�E���Ă��������B���̉�c�ł́A���N�������咣����x�����[�V��\�Ȃǂ̍R�c�����A�Z���ւ̔픘�e���͔F�߂��Ȃ��ƌ��_�����B���������̌�̃f�[�^��O�ɂ��āA����IAEA�Ȃǂ̐��Ƃ��A�b��B�K���̑������픘�e���ł��邱�Ƃ�F�߂���Ȃ��Ȃ����B�`�F���m�u�C�����̂̔�Q�͂ł��邾�������߂Ɍ������������A�Ƃ����l�X�̓w�͂͂��ꂩ��������ł��낤���A�����������f�[�^�����������l�X�̊�]������čs�����Ƃ����҂������B
�@����A���ː��e�����������s���Ă���L���E���茴�������҂Ɋւ���ŋ߂̃f�[�^�ɂ����Ă��A����܂Ŕ픘�e���Ƃ��ĔF�߂�Ă����K�����ɉ����āA�z��n�A�ċz��n�A������n�����Ƃ������K���ȊO�ɂ�鎀�S�̑���������ڂ���Ă���B���N�r�_�[�g���Ɋւ���픘�e���́A���������Ӗ��ł����ڂ������̂ł���B
�@