周辺30km圏避難住民の外部被曝量の評価
今中哲二,小出裕章
京都大学原子炉実験所
はじめに
チェルノブイリ原発4号炉が爆発炎上したのは,1986年4月26日午前1時24分(モスクワ時間)の少し前であった.原発職員が住んでいるプリピャチ市(原発から3〜6km)住民の避難がはじまったのは,それから約36時間後の4月27日午後2時であった.1300台のバスを使って,住民4万5000人の避難が約3時間で完了したと言われている.図1に事故後のプリピャチ市内の空間放射線量率を示す1.避難がはじまった頃のプリピャチ市内の空間線量率は,数100mR/h(ミリレントゲン/時)まで上昇していたことがわかる.

図1 事故後のプリピャチ市内の空間線量率
時間0が4月26日午前1時24分にあたる.
一方,プリピャチ市以外の周辺住民の避難が決定されたのは,事故から1週間たった5月2日のことであった.まず原発周辺10km圏の村落の避難が5月3日からはじまった.さらに周辺30km圏内の残りの村落の避難が行なわれ,5月6日にはほぼ終了した.プリピャチ市民を含め,結局13万5000人の住民がチェルノブイリ原発周辺30km圏から避難した1.
1986年8月にソ連政府がIAEA(国際原子力機関)に提出した事故報告書1(以下86年ソ連報告書)に基づくと,事故による被曝によって急性の放射線障害が現われたのは203人で,その全員が原発職員と消防士であった.そのうち28人が3カ月以内に死亡し,事故による死者は,破壊された原子炉建屋に閉じ込められた1人,事故当日に火傷で死亡した1人,他の原因による死者1人を加えて合計31人であった.一方,周辺住民の間には1件の急性放射線障害もなかったとされている.周辺住民に1件の急性放射線障害もなかったという86年ソ連報告書の見解は,ソ連の崩壊後もIAEA,WHOなどにうけ継がれ現在におよんでいる2−4.
チェルノブイリ事故当時のソ連において最も大きな権力をもっていたのはソ連共産党である.その中枢である共産党中央委員会政治局に,事故対策の基本方針を決めるため「事故対策作業グループ」が設置された.ソ連崩壊後の1992年4月,その事故対策作業グループの秘密議事録が暴露された5,6.その議事録によると,チェルノブイリ周辺住民に多くの急性放射線障害があったことが,共産党中央へ報告されていた.たとえば,1986年5月6日の議事録にはつぎのような記述がある.「病院収容者は3454人に達する.うち入院治療中は2609人で幼児471人を含む.確かなデータによると放射線障害は367人でうち子供19人.34人が重症.モスクワ第6病院では,179人が入院治療中で幼児2人が含まれる」(くわしくは本書のヤロシンスカヤ論文参照,また秘密議事録中の被災者に関する記載は本書最後の今中論文にまとめてある).
一方,ロシア科学アカデミー・社会学研究所のルパンディンは,チェルノブイリ原発に隣接するベラルーシ・ゴメリ州のホイニキ地区において,1992年に医師の面接や地区中央病院のカルテの調査を独自に実施している7.その結果,残されていた事故当時の住民のカルテから82件の放射線被曝例をみいだし,うち8件に急性放射線障害を確認している.ルパンディンはチェルノブイリ周辺30km圏全体では少なくとも1000件の急性障害があったであろうと述べている(くわしくは本書のルパンディン論文参照).
共産党秘密議事録の記載やルパンディンの報告は,周辺住民において急性放射線障害は1件もなかったとする,旧ソ連当局やIAEAなどの見解とまったく反するものである.
本稿では,最近明らかになった事故直後の汚染データなどを用いて,30km圏から避難した住民の外部被曝量評価を試みる.その結果を基に周辺住民において急性放射線障害を引き起こすほどの被曝があり得たかどうかを検討する.
急性放射線障害を生じるめやす被曝量
「急性放射線障害」という言葉そのものにあいまいさがともなうので,どの程度の被曝で急性放射線障害が起きると一概に決めることはできない.古くから,一度に1シーベルト以上の全身被曝をうけると,しばらくして吐き気,嘔吐といった急性障害の「前駆症状」が生じ,一方,0.25シーベルト以下では急性障害は生じないとされてきた.中川は,こうした「常識」は,広島・長崎原爆で観察された遠距離における急性障害例を無視して得られた結論であり,放射線影響を過小に評価していると批判している8,9.
ICRP(国際放射線防護委員会)によると10,11,感受性が大きいのは生殖細胞で,男性の場合0.15シーベルトの被曝で精子数の顕著な減少が観察される.また,造血器官に関連しては,0.5シーベルトの骨髄被曝で造血機能に低下が生じるとしている.
どのような症状に着目するかで,急性放射線障害が生じる被曝量は変わってくるし,また被曝線量率や全身被曝か部分被曝かといった被曝のうけ方も関係するであろう.さらに,年齢や健康状態といった個人の感受性によっても変わってくる.
ここでは,ICRPの見解を参考に,0.5シーベルトの外部被曝量をもって,急性放射線障害があり得たかどうかの「めやす被曝量」としておく.
事故直後のデータ
事故直後のチェルノブイリ原発周辺の放射能汚染状況について,86年ソ連報告書に図1のような断片的なデータが含まれていたものの,原発周辺全体の汚染状況を評価できるようなものはなかった.86年ソ連報告書は,それまでの秘密主義に比べ,西側専門家が驚くほど大部なものであったが,当時のソ連ではチェルノブイリ事故に関する情報は基本的に秘密事項であった.図2は,事故に関する情報の機密体制を強化するよう指令したソ連政府の通達である.
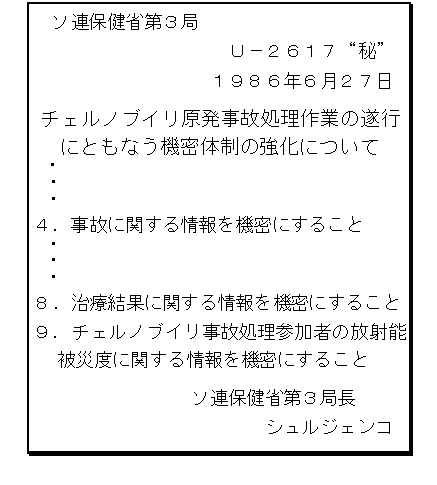
図2 チェルノブイリ事故に関する情報の機密体制強化を指令するソ連政府の通達
ヤロシンスカヤからの情報を基に今中が作成.
ソ連の消滅によって,機密体制そのものはなくなったが,事故当時に重要な立場にあった人々の多くがいまも健在である.こうした状況は,事故当時に発表されたデータはもちろんのこと,その後のデータについても,データの“質”に対して十分に注意を払う必要があることを示唆している.
事故から10年をへた1996年3月,EU(ヨーロッパ委員会)とCIS3カ国(ベラルーシ,ウクライナ,ロシア)の共同研究の報告会がミンスクで開催された12.その共同研究レポートのなかに,事故直後の興味深いデータがいくつか発表されている.ここではそれらのデータに基づいて外部被曝量評価を試みる.
5月1日の空間線量率データ
図3は事故発生から5日後の1986年5月1日における,原発周辺30km圏内の各居住区の空間線量率データである13.GM管式測定器を用いて地上1mで測定された値である.原発北方6kmのクラースノエ村で最大値(380mR/h)が認められる.自然放射線によるバックグランドは通常0.01mR/h程度なので,クラースノエの値はその3万8000倍である.そこに20分ほどいると,日本などの法令で定められている一般住民の年間被曝限度(1ミリシーベルト)に達するといった,とんでもないほどの汚染である.
30km圏全体ではかなりのバラツキがあるものの,概して原発の北方に大きな値が認められる.プリピャチ市以外の30km圏住民が避難したのは5月3日から6日にかけてであるから,これらの居住区の住民は1週間から10日ほど図3のような状況の中での生活を余儀なくさせられたことになる.
図3のようなデータが,事故直後から避難の日までそろっていれば,毎日の値を足し算することでだいたいの外部被曝量を見積もれるが,残念ながら,データが発表されているのは5月1日についてのみである.
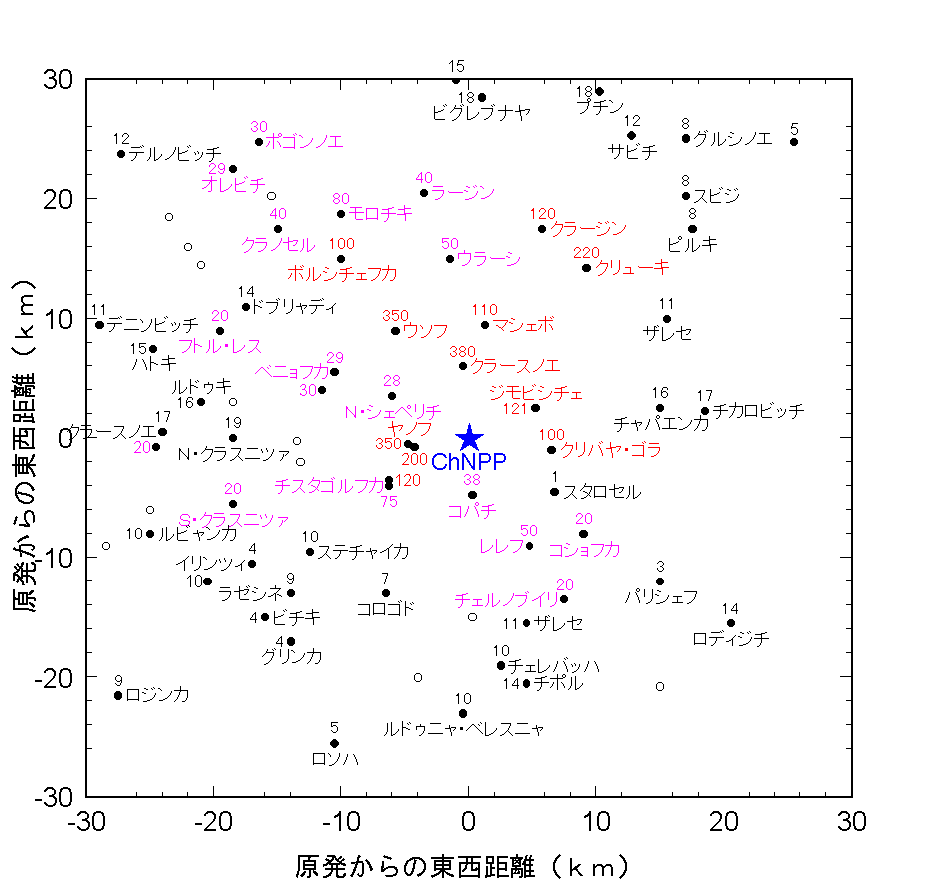
図3 1986年5月1日におけるチェルノブイリ原発周辺30km圏の各居住区の空間線量率(mR/h)13
居住区名は別の資料で調べて今中が記入した.元のデータはm Gy/h表示であるがmR/hへ換算した.
空間線量率の変化データ
30km圏住民が被曝をうけたのは事故から10日間程度であるが,その間の空間線量率の変化のしかたを計算できれば,図3に示したデータと組み合わせて,各居住区での外部被曝量を計算できることになる.
図4は,原発北方ベラルーシ側のホイニキ地区の空間線量率の変化データ14で,縦軸の値はセシウム137の沈着密度(1Ci/km2)当りの空間線量率(mR/h)で表してある.◆印が測定データで,2つの線(実線と点線)がわれわれの計算値である.測定データがはじまっているのは事故から5日目であり,それ以前の変化については計算に頼ることになる.
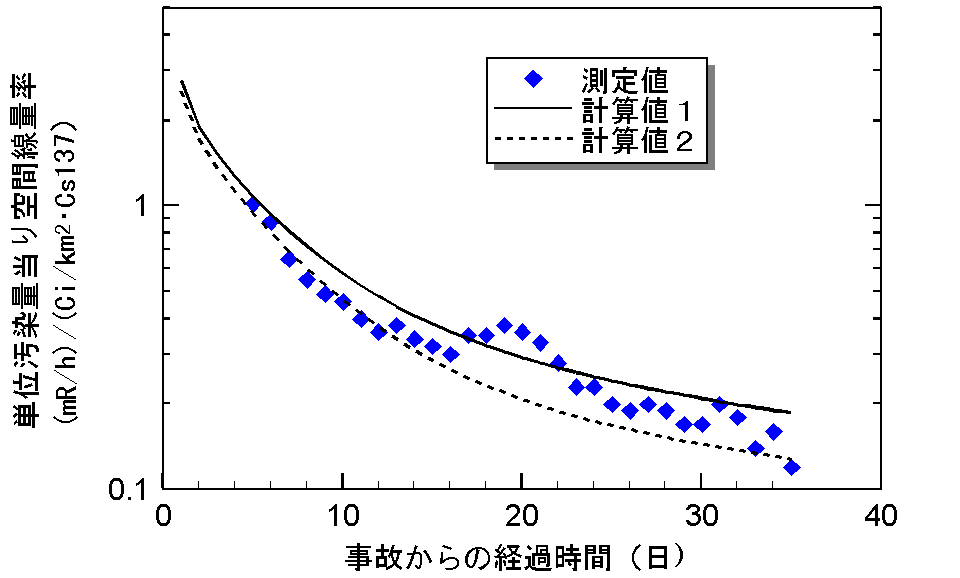
図4 セシウム137単位沈着量当りの空間線量率の変化
実線(計算値1)の方は,イズラエリらが報告している原発近傍での各放射能の沈着比15とそれぞれの放射能の空間線量率換算係数を用いて(表1),各放射能からの地上1mでの空間線量率を計算し,それらの値を足し合わせて得られたものである.図4から分かるように,30km周辺住民の被曝が問題になる事故から10日目までは,実線の値は測定値よりも大きい.
そこで,ジルコニウム95とバリウム140の沈着比を表1の半分にして空間線量率の変化を計算したものが図4の点線(計算値2)である.点線の方は測定値の最初の部分とよく一致しており,測定データのない事故後5日間の空間線量率の変化を推測するのに有効と考えられる.
表1 原発近傍に沈着した放射能の組成比(セシウム137=1)と空間線量率換算係数
|
核種 |
半減期 |
沈着組成比 (事故発生時換算) |
空間線量率換算係数** (m R/h)/(Ci/km2) |
|
ストロンチウム91 |
9.7時間 |
1.2* |
20 |
|
ジルコニウム95 |
65.5日 |
3.3 |
29 |
|
ジルコニウム97 |
17時間 |
1.6* |
29 |
|
ニオブ95 |
35日 |
3.3* |
15 |
|
モリブデン99 |
2.75日 |
7.5 |
2.8 |
|
ルテニウム103 |
39日 |
5.3 |
9.6 |
|
ルテニウム106 |
367日 |
1.3 |
3.7 |
|
ヨウ素131 |
8.04日 |
20 |
7.6 |
|
ヨウ素133 |
21時間 |
40* |
12 |
|
ヨウ素135 |
6.7時間 |
35* |
34 |
|
テルル132 |
3.25日 |
33 |
46 |
|
セシウム134 |
2.05年 |
0.5* |
29 |
|
セシウム136 |
13日 |
0.3* |
39 |
|
セシウム137 |
30年 |
1 |
11 |
|
バリウム140 |
12.8日 |
3.6 |
43 |
|
ランタン140 |
1.67日 |
3.6* |
39 |
|
セリウム141 |
32.3日 |
3.5* |
1.8 |
|
セリウム143 |
1.38日 |
3.1* |
4.9 |
|
セリウム144 |
284日 |
2 |
0.55 |
*:他の核種の沈着比を参考にして今中が決めた値.
**:換算係数は今中らのグループが計算して求めた値.
外部被曝量の計算方法の結果
ここでは,地表に沈着した放射能からの外部被曝と大気中の放射能雲からの外部被曝を計算する.
まず,以下の2つの仮定をおく.
A.各居住区での放射能の沈着は,4月27日12時に一度に起きたと仮定する.
B.各居住区の空間線量率の相対的な変化のしかたは,図4の点線と同じであったとする.つまり沈着した各放射能の組成比は30km圏内で同じであったと仮定する.
4月26日の最初の爆発にともなう放射能雲は西から北西方向に流され,27日から28日にかけて北から北東方向,29日以降は南向きに流されたとされている16.30km圏内全域で一度に沈着が生じたとする仮定Aは大胆ではあるが,図1で最も大きな値を示している原発北方の居住区についてはそれほどまずい仮定ではないであろう.仮定Bも,もちろん厳密には成立しないが,急性放射線障害の有無を検討するという本稿の目的の範囲では許される仮定であろう.
ここでは,図3に示されているデータポイントのうち,表2に示した4つの居住区について外部被曝量を計算する.クラースノエ村は図3で最も空間線量率の大きかった村で,ボルシチェフカ村はルパンディン論文で典型的な急性放射線障害例が報告されている村である.ウソフ村とチェルノブイリ市については,後に述べるリフタリョフらの論文17においても外部被曝が評価されており,われわれの評価と比較できる.
表2 30km圏内のいくつかの居住区での住民避難までの外部被曝量
|
居住区 |
5月1日の空間線量率 (mR/h) |
セシウム137沈着量 (Ci/ラ km2) |
避難実施日* |
地表汚染からの外部被曝(Sv) |
放射能雲からの外部被曝** (Sv) |
合計外部被曝量*** (Sv) |
|
|
ケース1 |
ケース2 |
||||||
|
クラースノエ村 |
380 |
470 |
(5月3日) |
0.30 |
0.030 |
0.007 |
0.32 |
|
ウソフ村 |
350 |
430 |
5月3日 |
0.28 |
0.028 |
0.006 |
0.29 |
|
ボルシチェフカ村 |
100 |
120 |
(5月5日) |
0.09 |
0.008 |
0.002 |
0.10 |
|
チェルノブイリ市 |
20 |
25 |
5月5日 |
0.02 |
0.002 |
0.0003 |
0.02 |
* リフタリョフ論文17より.( )内は近くの村落と比較した推測.
** ケース1とケース2は沈着速度が異なる(本文参照).
*** (合計外部被曝量)=(地表汚染からの外部被曝)+ ((ケース1の値)エ (ケース2の値))1/2.
地表汚染からの外部被曝
表2の第2列は,図3に示されている5月1日の各居住区の空間線量率である.一方,図4の点線から,5月1日12時(約5.5日後)におけるセシウム137沈着量当りの空間線量率は,0.805 [(mR/h)/(Ci/km2)]である.したがって,たとえばクラースノエ村のセシウム137沈着量は,380÷0.805=470 Ci/km2となる.表2の第3列はそうして求めたセシウム137沈着量である.第4列には,各居住区の避難実施日を示してある.放射能が沈着したのは4月27日12時と仮定しているので,その時刻から避難実施日の12時までの空間線量率を積分して,各居住区の積算空間線量D(R,レントゲン)を求めた.
空間線量Dは空気中を飛び交っているガンマ線の量(空気照射線量)を示しているが,その値から人々の被曝量H(Sv,シーベルト)を求めるにはいくつかの換算係数を掛ける必要がある.ここでは以下の式を用いた.
H = C3 ? C2 ? C1 ? D
- C1:空気吸収線量換算係数(=0.0087 Gy/R).空気照射線量(R)から空気吸収線量(Gy,グレイ)への換算,
- C2:人体被曝量換算係数(=0.82 Sv/Gy).空気吸収線量(Gy)から人体被曝量(Sv,シーベルト)への換算,
- C3:居住遮蔽係数(=0.61).屋外・屋内にいる時間と建物の遮蔽効果を考慮した係数.
それぞれの係数値はリフタリョフ論文17に示されている値をそのまま採用した.
表2の第5列が地表に沈着した放射能による避難するまでの外部被曝量(シーベルト)である.
放射能雲からの外部被曝
各居住区での空気中放射能濃度の測定値はまったくないが,ここでは,地表の放射能汚染量から各放射能の空気中放射能濃度を逆算して放射能雲からの外部被曝量を求める.
一般に,積算空気中濃度と地表汚染量との関係はつぎの式であらわされる.
(地表汚染密度,Ci/km2)
=(沈着速度,m/s)? (積算空気中濃度,(Ci/m3)・s)
ここで,
上記の式を書き換えると,
(積算空気中濃度)=(地表汚染密度)/(沈着速度)
となり,沈着速度が分かれば積算空気中濃度を求めることができる.
一方,放射能雲からの外部被曝量は,
(放射能雲外部被曝,Sv)
=0.61? (放射能雲被曝係数)エ (積算空気中濃度)
で求められる.ここで,0.61は居住遮蔽係数で,放射能雲被曝係数の単位は,Sv/[(Ci/m3)・s]である.
沈着速度の値については,実際の値は不明であるが,ここでは米国ラスムッセン報告18,19を参考に以下の2つのケースを用いた.
- ケース1:ヨウ素については0.005m/s,その他は0.002m/s,
- ケース2:すべての放射能について0.01m/s.
また,放射能雲被曝係数についても,ラスムッセン報告19の値を用いた.
放射能雲からの外部被曝の計算結果を表2の第6列と第7列に示してある.表の値から分かるように,放射能雲からの外部被曝は,地表汚染からの外部被曝に比べ,ケース1で約10%,ケース2で約2%であり,それほど大きな寄与を示していない.そこで,ケース1とケース2の幾何平均の値を放射能雲からの外部被曝とし,地表汚染からの外部被曝を加えて,合計外部被曝量とした(表2第8列).
5月1日の空間線量率が最大であったクラースノエ村での合計外部被曝量は0.32シーベルトとなった.外部被曝量の計算結果は,はじめに急性放射線障害の「めやす被曝量」とした0.5シーベルトには達していない.
ただし,表2の外部被曝量は各居住区の平均的な値を求めたものであり,個人々々がうけた被曝量は,その平均値のまわりにばらついているはずである.
居住区内での被曝量分布
各居住区内での個人の被曝分布を検討するうえで,興味深いデータが同じく1986年3月のEC/CISレポートに示されている.図5は,30km圏南東部のパリシェフ村の避難住民335人について事故当時の行動のアンケート調査を実施し,それに基づいて各個人の外部被曝の分布を評価したものである20.図から明らかなように,個人被曝量の分布は,対数正規分布できれいにあらわすことができる.
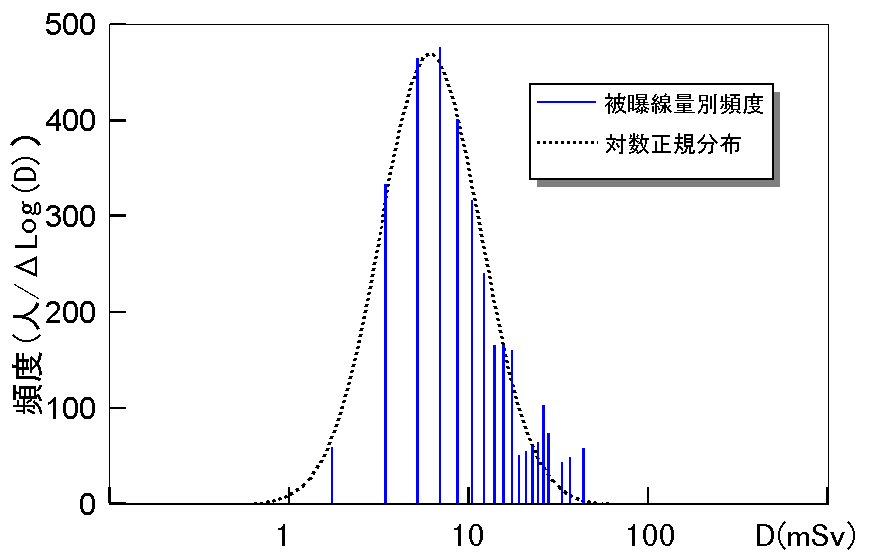
図5 パリシェフ村住民の外部被曝量分布
その対数正規分布のパラメータを計算し,95パーセンタイル被曝量(95%がその値より小さく,残りの5%が大きい被曝量)を求めると平均被曝量の2.85倍となった.
ここで,パリシェフ村の被曝量分布の形が30km圏の他の村々にも適用できると仮定すると,たとえばクラースノエ村の95パーセンタイル外部被曝量は,0.32? 2.85=0.91シーベルトとなる.つまり,クラースノエ村では住民の5%に0.91シーベルト以上の外部被曝があったことになる.
表3は,ここで着目している居住区において,0.5シーベルト以上,および1シーベルト以上の外部被曝があったと考えられる住民の割合である.
表3 外部被曝が0.5シーベルトと1シーベルトを越えた住民の割合
|
居住区 |
平均被曝量(Sv) |
0.5Svを越えた割合(%) |
1Svを越えた割合(%) |
|
クラースノエ村 |
0.32 |
24 |
3.5 |
|
ウソフ村 |
0.29 |
20 |
2.6 |
|
ボルシチェフカ村 |
0.10 |
0.5 |
~ 0 |
|
チェルノブイリ市 |
0.02 |
~ 0 |
~ 0 |
クラースノエ村では24%,ウソフ村では20%の住民の外部被曝が,急性放射線障害のめやす被曝量である0.5シーベルトを越えている.事故当時のウソフ村の人口は159人17とされているので,32人が0.5シーベルト以上,そのうち4人が1シーベルト以上の外部被曝となる.ボルシチェフカ村(5月1日空間線量率100mR/h)で0.5シーベルトを越えた住民の割合は0.5%である.
おおざっぱに判断するなら,図3の空間線量率で100mR/hを越えている11の居住区では急性放射線障害があり得たと考えてよいであろう.各居住区の人口は不明であるが,われわれの評価結果から,30km圏全体では少なくとも数100人の住民に急性放射線障害があり得たといえるであろう.
他の外部被曝量評価との比較
86年ソ連報告書には,避難住民の集団外部被曝量が原発からの距離別に示されている.その集団被曝量を人数で割って,距離別の平均外部被曝量を求めたものが表4である.プリピャチ市を除く3〜15kmの平均被曝量は0.45シーベルトで,15〜30kmでは0.05シーベルトである.評価方法の詳細は明らかではないが,86年ソ連報告書の値は,われわれの評価値(表2)よりも若干大きめである.86年ソ連報告書自体は,周辺住民において急性放射線障害はなかったと述べているが,居住区内での個人被曝量のバラツキを考えると,表4のデータは,むしろ急性放射線障害があった可能性を示していると言ってよいであろう.
表4 86年ソ連報告書の30km圏避難住民の外部被曝量
|
チェルノブイリ原発からの距離 |
居住区数 |
人数 (人) |
平均外部被曝量(Sv) |
|
3〜7 km |
5 |
7,000 |
0.54 |
|
7〜10 km |
4 |
9,000 |
0.46 |
|
10〜15 km |
10 |
8,200 |
0.35 |
|
15〜20 km |
16 |
11,600 |
0.052 |
|
20〜25 km |
20 |
14,900 |
0.060 |
|
25〜30 km |
16 |
39,200 |
0.046 |
|
3〜15 km平均 |
19 |
24,200 |
0.45 |
|
15〜30 km平均 |
52 |
65,700 |
0.050 |
|
3〜30 km平均 |
71 |
90,000 |
0.16 |
注:プリピャチ市避難住民4万5000人の平均外部被曝量は0.033Sv(上記には含まれていない).
一方,リフタリョフらは,30km圏から避難した住民3万6000人について,事故当時の行動のアンケート調査を行ない,各居住区の空間線量率測定データなどを基に各個人の外部被曝量を評価している17.プリピャチ市住民を除いた避難住民約1万7000人の平均外部被曝量は0.00182シーベルトである.そのうち0.25シーベルトを越えたのは5人で,個人被曝量の最大値は0.383シーベルトであったと報告している.
リフタリョフらの結果からは,避難住民に急性放射線障害を生じるような外部被曝があったとは考えがたい.表5は,ウソフ村とチェルノブイリ市について,彼らの値とわれわれの値を比較したものである.われわれの値はリフタリョフらの約3倍である.われわれの評価の根拠となっている図3のデータは,リフタリョフらのグループがEC/CIS共同研究のなかで作成したものと考えられるし,また換算係数や居住遮蔽係数など,われわれはリフタリョフ論文と同じ値を採用しており,本来同じような結果が得られるはずであるが,違いの原因は明らかでない.
表5 リフタリョフ論文17との外部被曝量の比較
|
居住区 |
平均外部被曝量 (Sv) |
A/B |
|
|
本研究 (A) |
リフタリョフ(B) |
||
|
ウソフ村 |
0.32 |
0.118 |
2.7 |
|
チェルノブイリ市 |
0.019 |
0.0060 |
3.2 |
リフタリョフ論文については,彼らがアンケート調査した人々のうち4000人については,高汚染地域やチェルノブイリ原発に立ち寄ったことを理由に評価対象から排除していること,また彼らの調査対象である30km圏のウクライナ側は,チェルノブイリ原発の主に南側であり,図1でも明らかなように,北のベラルーシ側に比べ汚染レベルが比較的小さかったことを指摘しておく.
まとめ
以上の結果をまとめると以下のようになる.
- 事故直後に避難した周辺居住区での平均外部被曝量の最大値は,クラースノエ村の0.32シーベルトであり,その値は,急性放射線障害のめやすである0.5シーベルトには達しなかった.
- 各居住区の個人の被曝量分布を考慮すると,汚染の大きな村では,20%以上の住民の外部被曝量が0.5シーベルトを越え,数%は1シーベルトを越えたと評価された.
- われわれの外部被曝量の値は,86年ソ連報告に比べると若干小さく,リフタリョフらと比べると約3倍となった.
- われわれの外部被曝量評価結果は,30km圏全体では少なくとも数100人に急性放射線障害があり得た可能性を示しており,チェルノブイリ事故直後に多数の周辺住民に急性放射線障害があったとする,共産党秘密議事録やルパンディン報告と一致するものである.
ここで強調しておきたいのは,今回のわれわれの評価には,呼吸や飲食物の摂取にともなう内部被曝を考慮していないことである.われわれの以前の評価21では,呼吸にともなう内部被曝は外部被曝の3分の1程度であった.呼吸よりも被曝への寄与が大きかったと思われる,飲食物摂取にともなう内部被曝の評価が難しいこともあり,ここでは内部被曝の評価は行なわなかった.外部被曝量だけからも,周辺住民に急性放射線障害が生じた可能性を明らかにすることができたと考えている.
ルパンディンの報告では,典型的な急性放射線障害例はボルシチェフカ村で認められている.嘔吐,衰弱といったその症状は1シーベルトを越える全身被曝があったことを示しているが,われわれの評価に基づくと,ボルシチェフカ村では1シーベルトを越えるような値にはならない.その患者は4月26日から27日にかけてプリピャチ川岸で釣りや日光浴をしていたと報告されており,われわれのモデルでは評価できないきわめて強い汚染にさらされたものであろう.
チェルノブイリ事故による急性放射線障害の問題について,最後にもう1つ指摘しておきたい.事故から1カ月余りたった1986年6月には,破壊された原子炉をコンクリートで覆ってしまう「石棺」を建設する工事がはじまった.つまり,それまでに原子炉建屋周辺に飛散していた核燃料や炉内構造物のガレキが片づけられたのである.
いったい誰がどのように,どれだけの被曝をうけながら作業をしたのであろうか.事故処理作業に最初に従事したのは,ソ連正規軍の若い兵士たちであったことが知られている.しかし,彼らがたいへんな被曝をうけながら作業にあたったことは確かであるが,事故から12年以上がたった今でもその詳細は明らかでない.
文献
- USSR State Commission on the Utilization of Atomic Energy, The Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant and Its Consequences, August 1986.
- IAEA, One Decade after Chernobyl: Summing Up the Consequences of the Accident, Proceedings of an International Conference, Vienna, 8-12 April 1996, STI/PUB/1001, IAEA, 1996.
- WHO, Health Consequences of the Chernobyl Accident: Results of the IPHECA Projects and Related National Programmes, Summary Report, WHO, 1995.
- OECD/NEA, Chernobyl: Ten Years on Radiological and Health Impact, November 1995.
- A. Yaroshinskaya, IZVESTIYA, April 24, 1992 (in Russian).
- A. Yaroshinskaya, Chernobyl: Top Secret, Drugie-berega, Moscow, 1992 (in Russian).
- V. Lupandin, Invisible Victims, NABAT No. 36, Minsk, October 1992 (in Russian).
- 中川保雄,放射線被曝の歴史,技術と人間,1991.
- 中川保雄,広島・長崎の原爆放射線影響研究:急性死・急性障害の過小評価,科学史研究,25巻,p20-33(1986).
- Nonstochastic Effects of Ionizing Radiation, ICRP Publication 41 (1984)
- 1990 Recommendations of ICRP, ICRP Publication 60.
- A. Karaoglou et.al. ed., The Radiological Consequences of the Chernobyl Accident, Proceedings of the 1st international conference 18-22 Mar 1996, EUR16544, EC.
- I. K. Baliff, V. Stepanenko ed., Retrospective Dosimetry and Dose Reconstruction, EUR 16540, EC(199) p.17.
- Ibid., p.109.
- Yu. A. Izrael et.al., Meteorology and Hydrology, 1987 No.2, pp.5-18 (in Russian).
- Yu. A. Izrael, Chernobyl: Radioactive Contamination in the Environment, Gidrometizdat, 1990 (in Russian).
- I. A. Likhtarev et.al., Retrospective Reconstruction of Individual and Collective External Gamma Doses of Population Evacuated after the Chernobyl Accident, Health Physics, 66(6): 643-652 (1994).
- USAEC, Reactor Safety Study, WASH-1400 Draft, August 1974.
- USNRC, Reactor Safety Study, WASH-1400, October 1975.
- op. ct. No.13, p.25.
- 今中哲二他,京都大学原子炉実験症第32回学術講演会報文集,1998年1月,p.93-100.