今中哲二
京都大学原子炉実験所
はじめに
私たちのグループ(京都大学原子炉実験所・原子力安全研究グループ)が原発の安全問題に積極的に取り組むきっかけになったのは,1973年にはじまった四国電力・伊方原発1号炉の設置許可取り消し裁判であった.同僚の瀬尾健(1994年6月逝去)は,原発が抱えている危険性がどの程度のものであるのか明らかにするため,伊方原発で最悪の事故が起きた場合の災害規模を評価する仕事に取り組んだ.彼の計算結果は,伊方原発1号炉(電気出力56万kW)で炉心溶融・格納容器破壊事故が発生すると,原発周辺で約5000人にもおよぶ急性死者,高濃度の放射能汚染は風下100㎞以上におよび,未曾有の災害となる可能性があるというものであった.しかし,当時の議論はあくまで机の上の「お話」であり,瀬尾の計算も原発の抱える危険性を理論的に提示したものにすぎなかった1.
商業用原発で発生した最初の大事故は,1979年3月に起きた米国スリーマイル島原発2号炉(100万kW)の事故であった.この事故では,炉心冷却に失敗し炉心の燃料の半分ほどが溶融したものの,格納容器の破壊は辛うじて免れたため,炉心の放射能が直接環境に放出されるという最悪の事態には至らなかった.
チェルノブイリ事故
1986年4月26日,旧ソ連ウクライナ共和国のチェルノブイリ原発4号炉(100万kW)において,原発で起こりうる最悪の事故の1つが発生した.原子炉出力の暴走・爆発にともない,原子炉と建屋が一瞬に破壊され,さらに炉心の黒鉛火災により大量の放射能放出が10日余り続いた(いつまで続いたか確かなところは未だに不明).事故の翌日から5月はじめにかけて原発周辺30kmから13万5000人の住民の強制避難が実施された.
私自身が,“チェルノブイリ”という聞き慣れない名前を初めて耳にしたのは,4月29日(旧天皇誕生日)の朝であったと記憶している.27日から28日にかけてスウェーデンやフィンランドなど北欧諸国で異常な放射能値が検出され,ソ連のチェルノブイリ原発で大事故が起きたらしい,というものだった.ニュースの扱いは時間と共にどんどん大きくなり,どうやらとんでもない大事故らしい,というのがはっきりしてきた.私たちの研究室でチェルノブイリからの放射能を最初に検出したのは5月3日に降った雨水からであった.ヨウ素131の存在を示すピークがはっきりと現われたのを覚えている.もちろん,日本中で放射能が検出され大騒ぎとなった.図1に,8000km離れた私たちの研究所まで飛んできた放射能の測定データを示しておく2.私たちの研究室では約20種類の放射能が検出された.チェルノブイリの放射能は,北半球のほぼ全域に達し,文字通り地球規模の放射能汚染をもたらした.
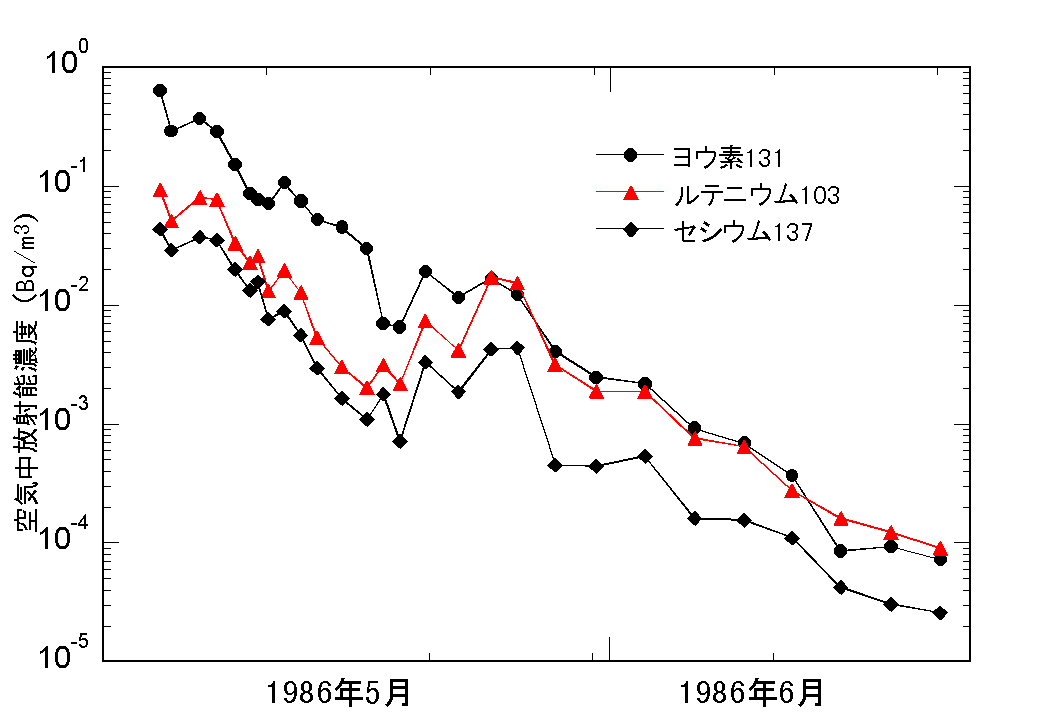
図1 京都大学原子炉実験所で観測されたチェルノブイリからの放射能の空気中濃度
チェルノブイリ原発でどのような事故が起き,どんな被害がもたされるのか分析する作業が,当然のこととして私たちのグループの仕事の1つとなった.瀬尾を中心に,世界中から汚染データを収集し,北半球規模での放射能汚染パターンの解析,災害規模の分析に取り組んだ3,4.1986年の末頃には,汚染のほぼ全体像をつかむことができたが,肝心の,もっとも被害の大きいはずのソ連国内の汚染は,8月にソ連政府がIAEA(国際原子力機関)に提出した事故報告書5のわずかなデータを使えるだけであった.
明るみに出た大規模汚染
ソ連国内では,チェルノブイリ事故に関する情報は一切が秘密扱いとされていた.IAEAへの報告書以降,ソ連国内の汚染についての新たな情報は全くといってよいほど発表されず,ソ連では放射能の測定すらろくにやられていないのでは,と私たちがいぶかるような状況が数年続いた.
ベルリンの壁が崩れたのは1989年11月である.東西冷戦終結への流れの中で,ソ連国内においても大きな地盤変動が起きつつあった.1989年2月,ベラルーシの新聞にチェルノブイリ周辺の汚染地図が公表された6.ソ連国内の民主化の動きや放射能対策を求める汚染地住民の突き上げに,共和国政府が抗せなくなって発表されたものであった.その地図をみて私たちが驚いたのは,高濃度の汚染地域が原発周辺だけでなく,200~300㎞も離れた所に,飛び地のように広がっていたことである.
表1と表2は,長期的にもっとも問題となる放射能であるセシウム137による汚染地域の面積と住民数を,現在の段階でまとめたものである.移住の対象となっている,セシウム137の汚染レベルが15Ci/km2以上の面積は3カ国合わせて1万km2余りにおよび,日本でいえば,福井県(4200km2),京都府(4600km2),大阪府(1900km2)の面積を合わせたものに相当している.そして,1Ci/km2以上のいわゆる「汚染地域」の面積14.5万km2は,本州の約60%に匹敵している.
|
表1 チェル事故被災3カ国のセシウム137汚染面積(単位:km2) |
|||||
|
国名 |
セシウム137の汚染レベル(Ci/km2) |
||||
|
1 ~ 5 |
5 ~ 15 |
15 ~ 40 |
40以上 |
1以上合計 |
|
|
ロシア |
48,800 |
5,720 |
2,100 |
300 |
56,920 |
|
ベラルーシ |
29,900 |
10,200 |
4,200 |
2,200 |
46,500 |
|
ウクライナ |
37,200 |
3,200 |
900 |
600 |
41,900 |
|
合計 |
115,900 |
19,120 |
7,200 |
3,100 |
145,320 |
|
表2 汚染地域の住民数(単位:万人) |
|||||
|
国名(データ集計時) |
セシウム137の汚染レベル(Ci/km2) |
||||
|
1 ~ 5 |
5 ~ 15 |
15 ~ 40 |
40以上 |
1以上合計 |
|
|
ロシア(1991.1.1) |
188.3 |
34.7 |
9.3 |
- |
232.3 |
|
ベラルーシ (1995) |
148.5 |
31.4 |
4.1 |
0.0283 |
184.0 |
|
ウクライナ(1995.1.1) |
173.2 |
65.3 |
1.9 |
- |
240.4 |
|
合計 |
510.0 |
131.4 |
15.3 |
0.0283 |
656.7 |
瀬尾と私が初めてソ連を訪れたのは1990年の夏であった12.ベラルーシ科学アカデミーとの接触に成功し,相互招待という形で実現したものであった.ミンスク,キエフ,モスクワの関連研究所を訪問して現地の様子を聞くとともに,ベラルーシの高汚染地域を訪問して放射線測定と土壌サンプリングを行なった.私たちの測定結果は,彼らが公表していた汚染データとほぼ一致するものであった13.また,ベラルーシの原子力研究所では,事故直後の放射能汚染に関する膨大なデータファイルを目にすることができた.しかし,まだソ連の時代であり,そうしたデータを私たちが利用できる段階ではなかった.
最初の共同研究
1991年末,チェルノブイリ事故に対して第1に責任を負うべきソ連が,広大な放射能汚染を残したまま消えてしまった.各共和国は独立し,放射能汚染対策の責任も各共和国が背負うことになる.秘密という壁はなくなり,研究者どうしの交流も容易になったことで,共同研究に取り組む環境が整っていった.
1993年,「チェルノブイリ原子力発電所4号炉事故による放射能放出量と事故直後の被曝線量評価に関する研究」(代表・瀬尾,330万円)というテーマでトヨタ財団に研究助成を申請したところ,幸いにして採択された.私たちとしては,向こうがもっている事故直後の放射能汚染データを基に,ベラルーシ国内の汚染パターンの解析をやり直し,初年度がうまく行けば,次年度はウクライナやロシアも含めた共同研究に拡大するつもりであった.1993年11月末,瀬尾と私が共同研究立ち上げのためミンスクに出かけた.私たちは,ミンスク滞在中に,研究の内容について実質的な議論を進め,作業全体のレールを作っておくつもりであったが,全くあてがはずれてしまうことになる.共同研究の相手は,それまでに交流ができていた研究者であったが,彼らの肩書きは研究所長や学長クラスで,いわばこちらより“格上”の相手であった.最初の会合で,日本側が提案しているような研究はベラルーシではとっくにやっている,外国人はデータをもって行っては勝手に発表してけしからん,というような話がはじまり,どうも勝手が違う事態になった.結局,日本人どうしの研究者であれば3時間もあれば十分なことに1週間もかかってしまい,とにかく共同研究を進める,という合意を取り付けただけの訪問であった.
年が明けた1994年1月,瀬尾は,データの解析方法,必要なデータの種類などをまとめた長文のメモを作りベラルーシ側にファックスで送った.彼はその直後から体の不調を訴え,結局そのメモが共同研究に関する彼の最後の仕事になった.4月になって,ベラルーシ側からファックスでデータが送られてきたが,データについての説明が不十分であったり,とにかく数字を並べただけといった感じのデータであった.残念ながら,積極的に共同作業を進めて行こう姿勢をベラルーシ側から感じることはできなかった.
結局その年の共同研究は,結局お茶を濁したような仕事しかできなかった,というのが私の本音である.ただ,この共同研究の経験を通じて,向こうの研究者の仕事の進め方やヒエラルヒー構造,彼らのものの考え方や習慣の違いに至るまで,私にとっては貴重な経験をすることができた.
新たな共同研究
瀬尾がいなくなったこともあって,1994年度は研究助成の申請を見送った.1995年度になってから気を取り直し,「ソ連崩壊後のロシア,ベラルーシ,ウクライナにおけるチェルノブイリ原発事故影響研究体制と研究の実状に関する調査研究」(代表・今中,200万円)というテーマでトヨタ財団に申請したところ採択される.前回の経験を踏まえ,共同研究のベースを,日本側とベラルーシ側といった平等な権利をもつチームどうしの関係から,今中をコーディネーターとする個人的なネットワークに意識的に置き換えた.また,研究の進め方も,頭をつき合わせて互いに議論するというより,各メンバーが自分のテーマをもってレポートを作成するというやり方にした.さらに,共同研究の立ち上げに柔軟性をもたせるため,申請時のメンバーは今中とベラルーシ・放射線生物学研究所のマツコの2人に限った.その後,個人的なツテを広げる形で,同僚の小出裕章と,ウクライナ・水圏生物学研究所のナスビット,ロシア・エコロジー進化問題研究所のリャプツェフに加わってもらった.
1996年4月ウィーンにおいてIAEAやWHOなどの共催で「チェルノブイリから10年:事故影響の総括」という国際会議が開かれた11.この会議の結論をまとめると,「チェルノブイリ事故は,原子力発電開発史上最悪の事故であったが,周辺住民への健康影響は大したことはなかった.事故の影響として唯一認められるのは,甲状腺ガンの増加であるが,このガンの致死率は小さい」というものである.いわゆる西側の学者のチェルノブイリ事故影響に対する見解の大勢はこの方向でかたまったといえよう.
私たちの新しい共同研究は,こうした流れに一石を投じることを意図していた.各国での事故影響研究の現状をまとめるとともに,IAEAなどが無視したり見落としている興味深い研究を紹介することによって,チェルノブイリ事故影響研究についての独自のレポート作りを目指した.被災3カ国では,IAEAなどの見解に反発している研究者は少なくなく,そうした研究者とのコンタクトは,私としてはかなりの手応えのある作業になっていった.
1996年度は,「ロシア,ベラルーシ,ウクライナにおけるチェルノブイリ原発事故影響研究と被災者救援活動の現状に関する調査研究」(380万円)というテーマでトヨタ財団に継続採択され,新たにヤロシンスカヤ(ロシア・ヤロシンスカヤチャリティ基金),マリコ(ベラルーシ・物理化学放射線問題研究所),ティーヒー(ウクライナ・環境教育情報センター),杉浦聡(日本チェルノブイリ基金,ミンスク事務所)の4名が加わった.1997年1月にモスクワで開いたミーティングの結果,次の5つのサブテーマに取り組むことになった.
- 各国でのチェルノブイリ事故影響研究体制とその現状のまとめ
- 各国での被災者追跡疫学研究の現状のまとめ
- 事故直後の周辺住民放射線急性障害に関する事実の収集と被曝線量評価
- 各国での被災者救援の制度と現状のまとめ
- 事故影響に関する興味深い研究の紹介
全体のコーディネーターとして私は,“ロシア流”の反対のやり方を心がけた.つまり,契約書のようなものは一切作らない,金の使い方についてはすべてオープンにする,ハッタリとか風呂敷の類は使わず,たとえ口約束でも約束したことはすべてやる,ということであった.この方針は,本人の予想以上にうまく行ったと思っている.期限通りとは行かなかったが,依頼したレポートはすべて出来上がった.
本書の内容
トヨタ財団からの研究助成は1997年10月で終わり,英語版と日本語版の報告書を作成する作業に入った.英語版の方は1998年3月,京都大学原子炉実験所のテクニカルレポートとして出版した15.本書は,その日本語版である.全体の構成は,以下の7つの章に分けた.
第1章「事故影響研究の概要」では,事故影響研究の経過と各国の関連法令の概要に関するレポートである.マリコ論文(No.2)は,旧ソ連当局の専門家がいかにチェルノブイリ事故影響の過小評価を試みてきたか,またIAEAやWHOの専門家がいかにそれを支援してきたかを述べている.グロジンスキー論文(No.3)は,ウクライナで観察されている人々の健康悪化の概要を述べるとともに,被曝影響に関する自分たちの実験データを引用しながら,低レベル被曝の危険性について警告している.ナスビット論文(No.4),マツコ論文(No.5)およびリャプツェフ論文(No.6)は,それぞれウクライナ,ベラルーシ,ロシアでの事故影響研究の概要と関連法令についてまとめた報告である.
第2章「放射能汚染データとその解析」は,非専門家には少々読みづらいかと思われれるが,いずれも放射能汚染に関するユニークな論文4編である.マリコ論文(No.7)は放射能汚染データを総合的に分析し,長期的な被曝量とそれにともなうガン影響について論じた力作である.No.8は,気象の専門家である水間満郎氏(京都大学原子炉実験所)に,共同研究の枠外で原稿を依頼したものである.チェルノブイリ周辺での観測データに基づく気象学的解析によって,事故直後の放射能汚染の形成プロセスについて興味深い結果が得られている.クナティコ論文(No.9)では,ベラルーシに沈着したセシウム137とヨウ素131の放射能比が詳細に解析されている.ボンダレンコ論文(No.10)では,チェルノブイリ原発周辺の土壌サンプルを用いた溶出実験によりウラン同位体比を調べたところ最大で27%という濃縮度のウランを検出している.その理由は確定されていないが,今後大きな論議を呼ぶ可能性のある結果である.
第3章「周辺住民の急性放射線障害」は,旧ソ連当局やIAEAなどが一貫して否定してきた,チェルノブイリ原発周辺住民の急性放射線障害の問題に焦点をあてている.ヤロシンスカヤの第1論文(No.11)は,旧ソ連共産党中央委員会政治局に設置された事故対策作業グループの秘密議事録から,事故直後に多数の住民の急性放射線障害が報告されていたことを明らかにしている.第2論文(No.13)では,ソ連時代の当局者がいかに無責任であったかを当時の書簡や資料を基に述べている.ルパンディン論文(No.12)は,チェルノブイリ原発に隣接するベラルーシ・ゴメリ州ホイニキ地区の地区中央病院に残されていたカルテを調査し,事故直後の周辺住民に急性放射線障害が認められていたことを明らかにしている.今中論文(No.14)は,最近明らかにされたデータなどを基に,周辺住民が避難するまでの外部被曝量を評価し,急性放射線障害が十分起こり得たことを示している.
第4章「疫学研究と健康統計データ」では,マツコ論文(No.15)とリャプツェフ論文(No.16)が,それぞれベラルーシとロシアについて,チェルノブイリ被災者を追跡調査するための疫学研究の現状についてまとめている.今中論文(No.17)は,リクビダートル(事故処理作業従事者)の健康状態が悪化しているというロシア・リャザン州のレポートの内容を紹介したものである.死亡率,ガン発生率,疾病障害者率といった健康指標の悪化が,1986年4-6月にかけて作業に従事したリクビダートルで顕著に認められている.ゴドレフスキー論文(No.18)は,ウクライナ・ジトーミル州ルギヌイ地区中央病院に勤務する著者らがまとめた地区住民の健康データである.デルガド論文(No.19)は,ロシア・ツーラ州内の各地区における健康データのまとめである.どちらの論文も現地の状況を知るうえで貴重な報告である.
第5章「個別の健康影響」は,甲状腺ガン,眼のレンズの混濁,先天性障害といった個別の問題を扱ったベラルーシからの論文4つである.いずれもチェルノブイリ事故による放射線被曝の結果として,被災地の人々に深刻な健康影響が現れつつあることを論じている.菅谷論文(No.20)ではベラルーシの子供の甲状腺ガンデータがまとめられている.菅谷昭氏は甲状腺治療の専門家で,信州大学医学部を退職したのち1996年1月よりミンスクの甲状腺ガンセンターに勤務している.マリコ論文(No.21)は,ベラルーシの大人の甲状腺ガンについて解析を行ない,事故による被害の大きさとしては子供甲状腺ガンの数よりも大人の方が大きいことを明らかにしている.アリンチン論文(No.22)は,汚染地域の子供の眼の水晶体混濁について調査し,対照グループに比べ汚染地域の子供たちの水晶体混濁が多いことを報告している.著者らは,水晶体の混濁が将来の白内障につながることを懸念している.ラズューク論文(No.23)は汚染地域における先天性障害の増加を報告している.彼らの調査は,チェルノブイリ事故以前から継続して実施されているものであり,その意義は非常に大きい.共著者の佐藤幸男氏(広島文化女子短期大学)は,放射線被曝による先天異常の専門家で,以前勤務していた広島大学原爆放射能医学研究所のときより彼らとの共同研究を継続している.
第6章「放射線生物学」の6編は,やや専門的になるが,染色体異常や生化学的パラメータの変化といった,放射線生物学的影響を論じている.ミハレービッチの第1論文(No.24)では,事故の数カ月後に実施した検査を含め,汚染地域の子供たちにおいて末梢血リンパ球の染色体異常頻度が増加していることを報告している.染色体異常から推定される被曝量は,物理的な手法により後に推定された被曝量より大きな値であった.第2論文(No.25)では,汚染地域の子供たちに現在でもかなり大きなレベルでリンパ球細胞の変異が観察されている.ゴンチャロワ論文(No.26)は,チェルノブイリ原発近傍を含め,汚染地域で野ネズミを捕獲し,その染色体の異常や構造変化を調査したものである.上記3論文はいずれも,事故直後に比べ被曝レベルが減少した最近においても,生体中では高レベルの細胞変異が継続していることを明らかにしている.シェフチェンコの第1論文(No27)は,染色体異常の観察データから人々の被曝量を推定した論文である.チェルノブイリ被災者,セミパラチンスク核実験場からの放射能汚染をうけたロシア・アルタイ地方の住民,プルトニウム工場からの放射性廃水によって汚染された南ウラル・テチャ川流域の住民,さらに米国スリーマイル島原発周辺住民についての被曝量推定結果を示している.スリーマイル島原発周辺住民からは,0.6~0.9グレイという,公式報告の被曝量からはかけ離れた値が得られている.第2論文(No.28)は,染色体異常データから被曝量を推定する手法についての解説である.ブルラコワ論文(No.29)は,本書ではもっとも難解な論文と思われるが,動物実験データと被曝集団の検査データを基に,放射線被曝が生体中のさまざまなバランス調節システムにおよぼす影響を,種々の生化学的パラメータの変化を観察しながら論じたものである.低レベル・低放射線量率での被曝影響が従来考えられてきたものより大きいことを,線量・効果関係に関する新たな視点から説明している.
第7章「被災者救済の制度と活動」は,チェルノブイリ被災者を救済するための各国の法制度や,被災者をとりまく社会的状況についてまとめた4編である.ティーヒー論文(No.30)は,旧ソ連時代から現在のウクライナまで,さまざまな社会的問題のなかでウクライナのチェルノブイリ被災者がおかれてきた状況を的確に論じている.マリコ論文(No.31)では,旧ソ連当局が被災者救済に真剣に取り組まなかったこと,ベラルーシの当局や科学者たちがモスクワ中央と対立しながら独自の救済策を立案していった経過をまとめている.ヤロシンスカヤ論文(No.32)は,彼女がウクライナで新聞記者をしていた頃の個人的な経緯も含めながら,旧ソ連時代とロシアでのチェルノブイリ被災者救済政策の現状についてまとめている.ズゲルスキー論文(No.33)は,旧ソ連,ウクライナ,ベラルーシ,ロシアの被災者救済法の内容と問題点の紹介である.
付録「データと資料」は,共同研究を進めるなかで,今中が興味をもったデータやチェルノブイリ原発に関する資料をまとめたものである.
本書のテーマはかなり広範にわたっているが,チェルノブイリ事故影響に関するすべての問題を扱うことを意図したものではない.むしろ,たまたま共同研究の“アミ”にかかった論文をまとめたものであり,事故影響研究のほんの一端を紹介しているにすぎない.それでも,本書の内容が,チェルノブイリ事故影響の問題を考えるにあたって貴重な情報を提供するものであることは,編集に携わって者として確信している.
文献
- 瀬尾健ほか,「原発の安全上欠陥」,第三書館,1979.
- T.Imanaka and H.Koide, "Faalout in Japan from Chernobyl", J. Environ. Radioactivity, 4(1986)149-53.
- 瀬尾健ほか, 「チェルノブイル原発事故における放射能放出量と環境汚染」, KUR第21回学術講演会, 1987年3月.
- 瀬尾健ほか,「チェルノブイリ事故による放出放射能」, 科学, 58 No.2 (1988)108-117.
- USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy, “The Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant and Its Consequences”, August 1986.
- Sovietskaya Belorussia, February 9, 1989.
- Izrael Yu.A. et.al., Meteorology and Hydrology, 1994, No.5, pp.5-9 (in Russian).
- Stepanenko V.F. et.al., Proc. 2nd Hiroshima Intern. Symp. July 23-25, 1996, RIRBM, Hiroshima Univ., pp.31-84.
- Malko M.V., KURRI-KR-21, pp.246-256, 1998.
- National Report of Ukraine, MinChernobyl, 1996 (in Russian).
- Firsova D., Chernobyl: Catastrophe Continues, Moskva, 1990, No.11 pp.138-148 (in Russian).
- 瀬尾健,チェルノブイリ旅日記,風媒社,1992.
- T. Imanaka, T. Seo, H. Koide; J.Radioanal. Nucl. Chem. Let., 154(1991)111.
- “One Decade after Chernobyl: Summing Up the Consequences of the Accident”, Proceedings of an International Conference, Vienna, 8-12 April 1996, STI/PUB/1001, IAEA, 1996.
- Imanaka T. ed., "Research Activities about the Radiological Consequences of the Chernobyl NPS Accident and Social Activities to Assist the Sufferers by the Accident", KURRI-KR-21, March 1998.