本稿は、「原子力資料情報室通信」No.275(1997年4月)に掲載された。
スリーマイル島原発周辺でのガン増加を示す新たな論文
今中哲二
京都大学原子炉実験所
1979年に発生した米国スリーマイル島原発2号炉(TMI−2、PWR、96万kW)事故から、今年の3月28日で18年が経過した。今年の2月、TMI周辺でガンが増加しており、その原因は事故時に放出された放射能であろう、という論文が発表された(S. Wingら、Journal of Environmental Health Perspective, Vol.105, January 1997)。TMI原発周辺でガンが増えているという話はずいぶん前から聞いていたが、その後の流れをキチンとフォローしておらず、不勉強で申しわけないが、Wing論文の内容について紹介しておきたい。
Wingらがその研究に取り組んだ動機のひとつは、TMI周辺住民の被曝量が、これまで定説とされたきた値よりかなり大きかったのではないかという疑問である。TMI事故の調査にあたった大統領委員会の報告では、周辺住民の最大被曝量は、自然放射線による年間被曝量レベルである、1ミリシーベルト程度とされている。しかし、事故直後に多くの周辺住民が、皮膚紅斑、おう吐、脱毛といった急性の放射線障害のような経験をしていたり、最近行われた周辺住民の染色体異常の検査に基づくと、事故直後の被曝量が600〜 900ミリシーベルトに達したという結果も得られている。
解析方法・結果
Wingらは、TMI周辺16kmの住民約16万人を対象に、まずその居住区を69地区に分け、事故前の1975年から事故後の1985年までの、各地区でのガン発生データを調べている。25ヶ所の病院・診療所の記録を調査した結果、対象期間に合計5493件のガン発生記録が見出された。やっかいな問題は、各地区住民の被曝量の見積もりである。ガン発生率と事故による被曝との関係を解析しようというのであるから、被曝量のめやすになるものが必要である。そこでWingらは、事故時の放射能放出パターンと気象条件に基づいて被曝量を計算している別の論文の値を使って、各地区に平均「相対被曝量」を割り当てている。つまり、その論文の「絶対値」はあてにならないが、地区間の「相対値」はそれなりに信頼できるだろう、という考え方である。各地区は、相対被曝量0のグループからから相対被曝量範囲1300-1600のグループにまで、9つの被曝量範囲にグループ分けされ解析の対象とされた。
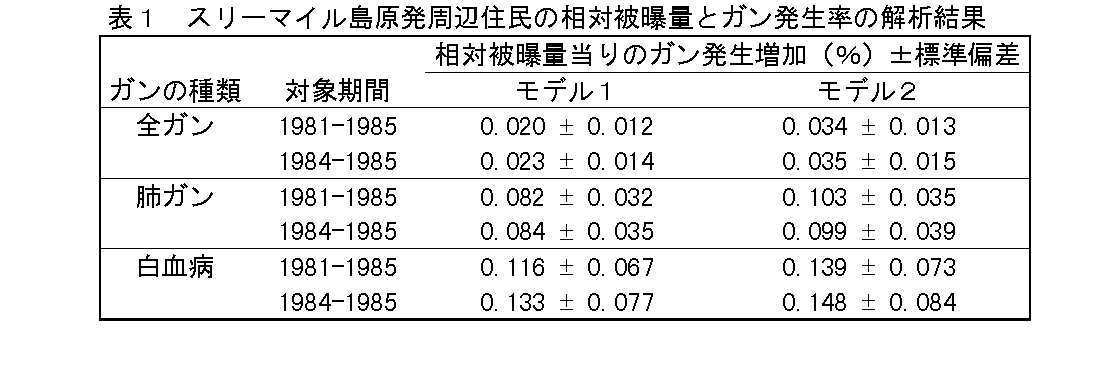
***
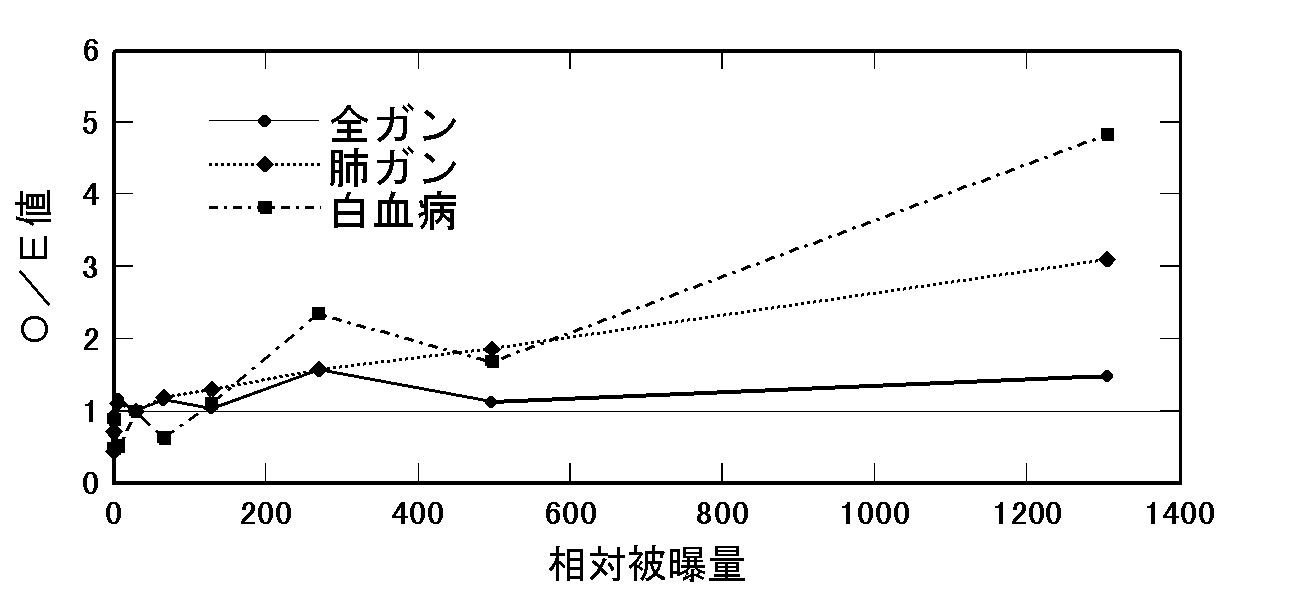
図1 相対被曝量とガン発生率の関係(1981〜85年、モデル2)
また、データの解析にあたっては、各地区の男女構成や年令分布の違い、さらには生活習慣の違いといった被曝量以外の要因が、解析結果に「見せかけ」の影響をもたらさないよう注意を払う必要がある。Wingらは、男女構成と年令分布について、各地区の条件が同じになるようデータ補正を行うモデル(モデル1)と、モデル1の要因に加えて収入と高等教育レベルについてもデータ補正を行うモデル(モデル2)とを用いている。収入や教育レベルの「見せかけ」効果については、事故前のデータの解析を行ってその効果の大きさを計算し、それに基づいて事故後のデータ補正を行っている。解析の対象期間は、被曝から発ガンまでの潜伏期を考慮し、1981〜85年の5年間と1984〜85年の2年間の2つである。
表1に解析結果を示す。表の値(相対被曝量当りのガン発生増加)は、相対被曝量とガン発生率との関係を示すグラフ上で、実際のデータと統計的に最もよく一致する直線を引いたときに、その直線の勾配がいくらになるかを示している。勾配の値がプラスであれば、被曝量とともにガン発生率が増加する関係にあり、マイナスであれば逆の関係である。±記号の後ろについている標準偏差は、その勾配値の統計的ばらつきの大きさを示すもので、たとえば0.0020±0.012とは、勾配の本当の値は0.0008〜0.0032の間にある可能性が大きい、ということを示している。表の値は、ばらつき範囲を考慮してもすべてプラスの範囲に入る。つまり、Wingらの解析結果は、全ガン、肺ガン、白血病のいずれについても、被曝量とともに発生率が増加することを統計的に有意に示している、ということになる。
図1は、論文の解析データのうち、1981〜85年のモデル2による相対被曝量とガン発生率の関係をプロットしたものである。縦軸のO/E値がガン発生率を示している。O/Eとは、(観察値)÷(期待値)のことで、この値が1(図の細い実線)であれば、その区分のガン発生率は調査集団全体と同じであり、1を越えていればそれより大きいことを示している。相対被曝量の小さいところは判りずらいが、いずれのガンにおいても、被曝量とともに発生率がほぼ直線的に増加していることが認められる。
Wing論文の問題提起
表1に示した解析結果を基に、相対被曝量1600が1ミリシーベルトに相当すると仮定して、1981−85年のモデル2について、1ミリシーベルトの被曝によるガンの増加割合を計算してみると、全ガンで54%、肺ガンで165%、白血病で222%ということになる。ちなみに、広島・長崎の被爆生存者追跡調査データから得られている増加割合は、1ミリシーベルト当り全ガン0.041%、肺ガン0.063%、白血病0.521%(寿命調査報告第11報より)であり、Wingらの値の方が400〜2600倍も大きな値である。この矛盾を説明するための仮説としては、
А.TMI周辺住民の被曝量は、定説に比べ 数100倍から数1000倍大きかった
B.TMIのような低線量被曝(ミリシーベ ルト程度)の発ガン効果の現れ方は、広島 ・長崎のような高被曝量(数100ミリシー ベルト程度)の場合とは全く異なっており、 単位被曝量当りの効果は低線量の方がはる かに大きい
といったことを思いつくが、今の段階で結論にまで踏み込んだことを言うのは難しい。とりあえずは、これからの課題ということでお茶を濁しておきたい。
本稿の読者がWing論文の内容で不思議に思われるのは、ガン調査の対象期間が、12年も前の1985年までにしか過ぎないことであろう。実は、Wingらが用いているガン発生と相対被曝量データは、1990年と1991年に発表されたHatchらの2つの論文(American Journal of Epidemiology, Vol.132, September 1990, American Journal of Public Health, Vol.81, June 1991)と同じものである 。Hatchらは、周辺住民がTMI電力会社を訴えた裁判の和解で設置されたTMI公衆基金の要請により、周辺住民の疫学調査に取りかかったものであった。Hatchらは、はじめの論文では、事故による被曝とガン発生増加との関係は認められないと結論し、後の論文では、TMI周辺では一時的にガンの増加は認められるが、その原因は精神的ストレスであろう(今中は6年前この論文を読み、煮え切らないことを言っているな、と思ったがそのまま忘れていた)と述べている。Hatchらの結論を受けて、TMI公衆基金はその後の調査を継続しなかったのであろう。
Wingらは、Hatchらの結論に疑問を抱き、Hatchらのデータを再解析したところ、全く正反対の結論に至った、というわけである。WingらとHatchらとでは、被曝量区分や解析対象期間の設定など解析方法に若干の違いはあるが、最も大きな違いは取り組みの姿勢であろう。Hatchらの研究では、定説どうりの被曝量によってガン影響が現われることなどあり得ないと、はじめから決めてかかっていたようである。同じ素材を用いて同じ料理を作ったが、料理人の腕と微妙なレシピーの違いで全く違う味になってしまった、というところであろうか。料理の味なら変わっても当然であるが、事実は一つである。
いずれにせよ、Wingらが主張しているように、1985年以降の調査にただちにとりかかる必要があろう。