発生出力と中性子線量
<本稿は「技術と人間」1999年12月号に掲載された>
一九九九年九月三十日
臨界事故は本当らしい、と思うようになったのは午後もしばらくたってからであった。被曝を受けた作業員三人が吐き気を訴えたりしてヘリコプターで千葉市の放射線医学総合研究所の病院に運ばれ、うち二人が意識不明というニュースを聞いてからである。吐き気や意識障害は急性放射線障害の特徴であり、核燃料転換工場でそのような大量被曝があったのなら臨界事故以外に考えられない、という納得の仕方であった。臨界事故というのは、核燃料工場や再処理工場などで、何かの拍子にウランやプルトニウムといった核燃料物質が一カ所に集まってしまい、核分裂連鎖反応を起こしてしまう事故である。一瞬(一秒以下)のうちにパワーバースト(出力暴走)が発生し、そのバーストにともなって容器が破壊されたり核燃料が飛び散ったりして終息する、その昔、原爆開発にともなって米国やソ連でちょくちょくあったようだが最近は聞いたことがない、というのが臨界事故に対する私の認識であった(炉物理を専門にしている小林圭二さんは、容器が壊れてないらしいと聞いて、すぐに再臨界のことが気になったそうである)。マスコミからの問い合わせ電話がいくつかあったものの、こちらが情報をもっているわけではないので、問い合わせは軽く受け流して普段通りに午後の仕事をこなした。
驚いたのは夕刻に帰宅しテレビのニュースを見てからであった。JCO周辺では依然として高いレベルのガンマ線が続いており周辺三五〇mの住民が避難していた、さらには四ミリシーベルト/時という高レベルの中性子が敷地境界で検出されているという。すなわち、臨界状態がいまだに続いており、収拾の見通しがない状況に陥っていたのであった。
作業員から急性放射線障害が出ていること、周辺住民の緊急避難が行われていること、事態収拾のメドがたっていないこと、これらのことは、日本の原子力開発史上最悪の事故が目の前で進行していることを示していた。
危機管理と情報管理
臨界状態の沈殿槽は「裸の原子炉」となり、強力な中性子とガンマ線を発していた。茨城県の事故対策本部は、午後一〇時半に半径一〇㎞圏内の屋内待避勧告を出すに至った。JCO職員による深夜の決死的な水抜き作業によって何とか臨界を終わらせることができたのは、十月一日の明け方であった。半径一〇㎞圏内の屋内退避勧告が解除されたのは十月一日午後四時半で、三五〇m圏の避難勧告は、二日の午後六時に解除された。JCO事故は一応の終息に向かうことになる。
「何か変だな」と私が感じ始めたのは十月一日の午後くらいからで、二日には確信に近くなっていた。何だか変なのは、放射能汚染に関するデータがまったく出てこなかったことであった。JCOの施設は臨界事故の発生を想定しておらず、事故を起こした転換試験棟の換気システムは通常の塵埃用フィルターしか装備していない。したがって、臨界事故にともなって発生した希ガスや揮発性ヨウ素は容易に外部に放出されたはずである。テレビに出てくる専門家は、JCO事故では敷地外への放射線もれはあったが、放射能もれはまったくなかったかのように語っていた。取材の電話をかけてくるマスコミ関係者にも放射能もれのことはほとんど頭にないようであった。事故が起きた東海村には、日本原子力研究所、核燃サイクル機構(旧動燃)、日本原子力発電など日本の第一級の原子力施設が集中している。放射能汚染の測定に関する多くの専門家がいるので、かなりのデータがとられていることは間違いなかった。しかし、その結果はまったく発表されなかった。
日本の原子力防災の考え方は、地元の自治体が国の専門家から助言を受けて対応することになっている。しかし、原子力安全委員会の「緊急助言者組織」が初会合を開いたのは、東海村で三五〇m圏の住民がとっくに避難した後の午後六時のことであった。JCO事故は、日本の原子力防災システムがまったく役に立たないことを事実で示していた。マスコミは、政府の「危機管理」がなっていない、と書き立てはじめた。
私の危惧は、「危機管理」のかけ声と同時に「情報管理」が進行しつつあることだった。「危機管理」をうまく行なうには情報を一元化する必要がある。となると、危機管理に情報管理がともなうのは当然のことかも知れない。JCO事故の放射能汚染に関する情報は科学技術庁に集められ、一括管理されているようだった。科学技術庁では、JCO事故がもたらすであろう原子力全体へのダメージを少しでも和らげるため、「放射線は漏れたけど放射能は漏れなかった」というストーリーが作られようとしていたのであろう。
京大工学部の荻野晃也さんは、十月三日に東海村の現場へ出向いてJCO周辺で土壌とヨモギを採取し、私の同僚の小出裕章さんに測定を依頼してきた。小出さんが四日にサンプルを受け取って測定を開始すると、あっけないほど簡単にヨウ素一三一が検出された。放射能汚染はなかったのではなく、測定結果が発表されていないか、意識的に測定されていないだけであった。私の方は、それまでに新聞報道されていたデータなどに基づいて、臨界事故で発生した出力や中性子線量の計算、核分裂でできた放射能量の計算などに取り組むことにした。情報管理をやらせないためには、こちらからドンドン情報を出して行くことが必要と考えたからであった。
臨界継続時の出力
臨界事故では、どれだけのウランが核分裂を起こしたか(出力)が事故の大きさを考えるうえでの基本的な情報である。通常の原子炉では、発生する中性子数や熱量を測定するための計器を備えているので、その測定データに基づいて原子炉出力を決めることができる。JCOの沈澱槽は勝手にできあがった原子炉であり、その出力を推定することは結構やっかいな仕事である。ここでは、非常に大ざっぱな方法であるが、事故時に測定された敷地境界での中性子線量率から、どの程度の規模の原子炉ができあがったかを見積もってみた。
臨界事故が発生したのは午前一〇時三五分であった。施設内ではガンマ線用のモニター警報が鳴り、五分後に所員はグラウンドに待避している。臨界事故を確実に検知するためには、中性子用のモニターを設置しておく必要がある。中性子の大部分(九九%以上)は核分裂反応と同時に放出されるため、連続して中性子を測定していれば臨界状態、すなわち核分裂反応の進行状況を把握できる。ところが、JCOの放射線管理システムは、臨界事故などもともと想定していないため、中性子用モニターやサーベイメータ(可搬型測定器)を備えていなかった。臨界事故が一度のパワーバーストで終わってしまったのなら、ガンマ線レベルもすみやかに落ちるはずであった。しかし、午前一一時半の敷地境界でのガンマ線量率は〇・八四ミリシーベルト/時と、一時間余りの被曝で公衆に対する年間被曝限度一ミリシーベルトにたっするレベルであった。一三時五六分、JCO職員が施設周辺五〇〇mの住民を避難させるよう東海村に対し要請した。一向に低下しないガンマ線量率は、臨界が継続していること、つまり沈澱槽での核分裂連鎖反応が継続していることを疑わせた。そのことを確認するには、核分裂反応にともなって放出される中性子を測定してみる必要があった。午後五時になってようやく、原研からもってきた中性子用サーベイメータによって中性子の測定が行われ、敷地境界で四ミリシーベルト/時という大変な値がでたのであった。この値は、翌朝に沈澱槽周辺の水を抜いて臨界が終息するまでほぼ一定であった。
敷地境界(「裸の原子炉」から八〇~一〇〇m)で四ミリシーベルト/時という中性子線量率が継続していたときの発生出力を見積もってみた。見積もりの方法は次の通りである。まず、「裸の原子炉」の出力が一ワットであると仮定したときの、八〇~一〇〇mの距離での中性子線量率を計算する。次に、実際の測定値がその何倍であったかを求めれば、そのときの出力がワット単位で得られることになる。見積もりの結果を表1に示す。中性子線量率の計算には、二種類のプログラム(DOTとMORSE)を用いた。DOTは二次元体系の計算プログラムでシンプルな体系に対し広範囲の計算が可能である。MORSEは三次元体系のプログラムで複雑な系の計算ができるが、広範囲の計算には不向きである。DOTの場合は、地表三mのところに点線源を設定し、地面と空気だけを考えて周辺での中性子線量率を計算した。この場合、沈澱槽や建物のよる遮蔽の効果は入っていないので、一ワット当りの中性子線量率は、明らかに実際よりも大きな値になってしまう。MORSE計算の場合は、沈澱槽自身と転換試験棟の遮蔽効果をシンプルなモデルで取り扱っている。MORSEの三つの計算の違いは、円筒の壁の厚さを一〇、二〇、五〇㎝と変えた効果を示している。
表1 臨界継続時の出力評価
評価の前提:距離80~100mでの中性子線量率が4ミリシーベルト/時
|
|
中性子線量率計算値 (ミリシーベルト/時) |
|
||
|
|
|
|
||
| DOT計算: | ||||
|
|
|
|
|
|
| MORSE計算: | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:MORSEでは、沈澱槽を直径50cm高さ20cmの円柱の水、建屋を外径10m高さ8mの円筒コンクリートでモデル化した.建屋の屋根はないものとし壁の厚さを変えて計算した.
表1の計算結果をながめて分かるように、沈澱槽自身や建物の遮蔽は、中性子線量率を六~二〇分の一に減らす程度の効果を示している。表には示していないが、ほかにもいろいろと計算をやってみた「感触」を基に、ここでは、MORSEのM―2の結果(七六〇ワット)を私の出力見積もりの最適値としておく。その誤差範囲は±一〇〇%(四〇〇~一六〇〇ワット)としておきたい。三十日午前一〇時三五分から翌朝四時三五分まで、七六〇ワットの出力が一八時間続いたとすると、臨界継続時、すなわち初期バーストを除いた期間の積算出力は約一四キロワット時となる。
私の最初の計算結果がまとまったのは十月五日であった。インターネットを通じて、発生出力、周辺中性子線量率、生成放射能量などの計算結果を多くの人に流したが、その時の臨界継続時積算出力の見積もりは、約一〇キロワット時(核分裂を起こしたウランの量にして約〇・五ミリグラム)であった。
バースト時の出力
今回の臨界事故の出力評価でやっかいなのは、最初のバーストで発生した出力の見積もりである。十一月四日に科学技術庁が発表した報告書では、原研などでの解析結果を基に、臨界終息までの出力を初期バースト部分(九月三十日一〇時三五分~一一時)と臨界継続部分(一一時~十月一日午前六時一五分)に分けて評価されている。そして、事故全体で発生した総出力のうち、四八%が最初のバースト時期に発生したことになっている。
科技庁報告の見積もり方法を簡単に説明しておこう。事故から三週間後の十月二〇日に沈澱槽の残存溶液サンプルを採取し、その中のウラン濃度と放射能濃度を測定した。ウラン一グラム当りどれだけの放射能が出来ていたかという値を基に、沈澱槽で起きた核分裂の総数を推定している。その核分裂数に基づくと、全体の積算出力は二二キロワット時となる。一方、初期バースト期をのぞいた、臨界継続時の出力は、先に述べた私の見積もりと同じ方法(ただし、二五〇m地点での中性子線量率の測定値と計算値を比較)を用いて、九月三十日午後八時四五分頃の出力が五一〇ワットであったと評価している。さらに、午後八時四五分までのなだらかな出力低下を考慮し、臨界継続時の積算出力を一一・七キロワット時としている。バースト時の積算出力は、全体(二二)から臨界継続時(一一・七)を差し引いて、一〇・三キロワット時であったとしている。
一見もっともらしくみえるこの評価は、報告書の中身を突っ込んで検討してみると問題だらけであることがわかる。まず、残存溶液から積算出力を評価する手法は、沈澱槽内の溶液量がわかっていることを前提としている。ところが、総ウラン量の計算は五六~六一リットルの液量で行ないながら、実際に残っていた液量は三七リットルであったと述べている。約二〇リットルのつじつまが合っていない。また、臨界継続時の前半には、ガンマ線のモニタリング記録から、なだらかな出力減少があったとしている。しかし、同じガンマ線モニターの記録と思われる図が二枚示されているが、臨界継続時の値がひと桁違っている、などといった問題がある。
ここでは、具体的な測定データを使って直接的な方法でバースト部分の見積もりを行ってみる。JCOから約二㎞離れた原研那賀研究所(核融合実験施設)の二つの中性子モニタリングポスト(距離一・七㎞と二㎞)では、JCO事故による最初のバーストにともなうピークが検出されていた。原子力安全委員会から発表されている資料を基に、二つのモニタリングポストの毎分計数率の変化を描いたものが図1である。臨界バーストは二つのモニタリングポストに「みごとな」データとして記録されている。科技庁報告をまとめた人たちは、バースト部分の大きさを評価するのに、なぜこのデータを用いなかったか不思議である。
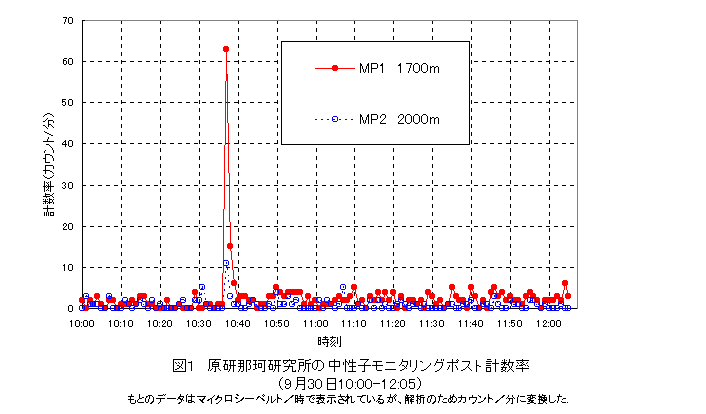
原研モニタリングポストのデータのうち、MP1の事故前の平均計数率は毎分一・〇三カウントである。バースト時の三分間の計数は八四カウントで、事故前の計数率をバックグラウンドとすると、八〇・九カウントとなる。バースト後の臨界継続時(一〇時四〇分~一二時五分)の平均計数率は毎分二・三三カウントであり、事故前のバックグラウンドを引くと毎分一・三〇カウントである。中性子線量率への換算計数を掛けると、バースト時三分間の中性子線量は〇・〇〇六マイクロシーベルトとなり、臨界継続時の中性子線量率は〇・〇〇五四マイクロシーベルト/時となる。臨界継続時間を一八時間とするとその間の中性子線量は約〇・一マイクロシーベルトとなる。すなわち、原研中性子モニタリングポストのデータに基づく私の評価では、最初の三分間のバーストの寄与は全体の約六%にしかならない。科技庁報告の四八%に比べて八分の一であり、両方の評価はどうみても矛盾している。
私の評価の問題点を述べておこう。私の評価では、バースト後の臨界継続時の出力は、一〇時四〇分から一二時までの平均の値を用いており、その値が一八時間一定であったとしている。ガンマ線量率の測定データなどをみると、臨界継続時の前半になだらかな出力低下があったようである。原研中性子モニタリングポストの事故全期間にわたるデータがあればよいのだが、この出力変化は私の評価には入っていない。科技庁報告では、午前一一時の出力が一一七〇ワットであったものが徐々に低下し、午後八時一五分には約半分の五一〇ワットとなり、それから一定の出力が翌午前三時三〇分まで続いた、と述べている。科技庁報告に従うと、最初の二時間分だけで臨界継続部分の出力を見積もると約二倍の過大評価となる。つまり、バースト部分の割合も約半分に見込んでいたことになる。しかし、その効果を修正したとしても、バースト部分の寄与はせいぜい全体の一割余りであり、矛盾の解消には至らない。バースト部分の寄与の評価は、事故全期間にわたる中性子モニタリングポストのデータが発表された段階で改めて見直すつもりであるが、当面の私の評価としては全体の六%としておく。
中性子線量と総発生出力
今回の事故の特徴のひとつは、被曝の主役が中性子だったことである。チェルノブイリのような原発事故の場合に問題となるのは環境に放出された放射能(核分裂生成物)であり、セシウム一三七とかヨウ素一三一といった放射能から放出されるガンマ線やベータ線による被曝が中心となる。中性子による環境中での被曝は、原発事故の場合一般的には問題にならない。JCO事故では、「裸」つまり周囲に遮蔽のない原子炉が突然できあがったため、核分裂進行中の沈澱槽から漏れ出る中性子が、数百mさらには数㎞先まで到達するような事態となった。
JCOの敷地外での中性子線量を評価するにあたって二種類の重要なデータが得られている。そのひとつは原研那賀研の中性子モニタリングポストのデータである。もうひとつのデータは、九月三十日午後七時頃からJCO敷地周辺一〇カ所余り(距離八〇~五四〇m)で午後七時頃から数時間おきに実施された中性子サーベイメータによる線量率測定である。後者のデータは事故発生から午後七時までの測定を欠いているが、原研労働組合は、ガンマ線量率サーベイデータの変化を用いてデータのない時刻の中性子線量率を推定し、臨界継続期間の中性子線量を見積もっている(毎日新聞十月十六日)。図2は、二種類の測定データと二種類の私の計算結果を示している。中性子モニタリングポストMP2(二㎞)での中性子線量は、バースト時ピークの大きさの比較から、MP1の一五%(〇・〇一五マイクロシーベルト)とした。また、原研労組のデータには、バースト分の寄与として約六%が上乗せしてある。私の二つの計算は、測定データに合うように線源強度(発生中性子数)を調整したものである。MORSEで遠方まで計算すると、かなりの時間を要し結果の精度も悪くなるので八〇〇mまでしか計算してない。測定、計算の四種類のデータは、ひとつの曲線上にあり、互いに整合性のよいことを示している。無遮蔽のDOT計算に比べ、沈澱槽と壁の遮蔽を考慮したMORSE計算の線源強度は九・三倍になっていることに注意して頂きたい。JCO事故を模擬した計算としては、DOTよりMORSEの方が優れている。事故による総発生出力の見積もりには、図2のMORSE計算の線源強度である一六・八キロワット時を採用しておきたい。この場合、核分裂を起こしたウランの量は〇・七四ミリグラムで、総核分裂数は一・九×一〇の一八乗となる。
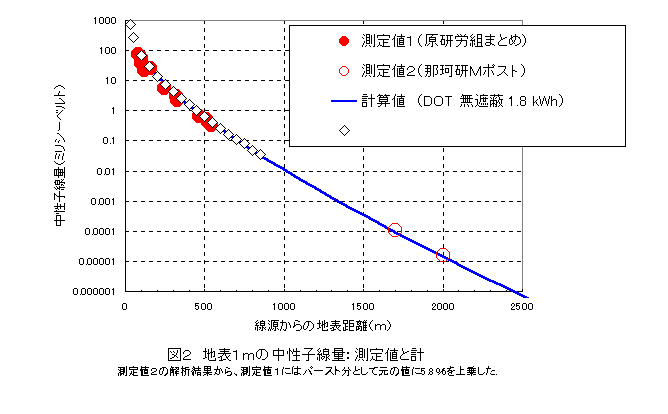
現在の日本の法令では、一般公衆に対する被曝限度は年間一ミリシーベルトである。原子力施設では、その敷地境界での被曝線量が年間一ミリシーベルトを越えないように管理され、それが守れなければ法律違反となる。JCO事故では、図2に示したように、沈澱槽から最短距離の敷地境界(八〇m)で一〇〇ミリシーベルト余りの中性子線量となり、約五〇〇mの範囲内で一ミリシーベルトを越える線量となった。ガンマ線量レベルは中性子線量の約一〇分の一程度であった。三五〇m圏の住民に午後三時の段階で避難が実施されたことと、図2に示した中性子線量は野外での線量であり家屋内にいれば建物による遮蔽効果(状況により数分の一)があることから、図に示した中性子線量をそのまま受けたわけではないが、近くに住んでいた人々に年間線量限度を超える被曝があったことは間違いない。
どれだけの数の人々が被曝したかという問題に答えるには、まずどれだけの被曝があれば「被曝した」というのかという問題を明らかにしておく必要がある。法令限度はさておき、職場において放射線作業従事者でもある私個人の感覚で表現させてもらうなら、〇・〇〇一ミリシーベルトの被曝は放射線を「ちょっとうけた」といった感じであり、〇・〇一ミリシーベルトでは「少しあびた」、〇・一ミリシーベルトとなると「けっこう被曝した」といった感じである。職務上、研究上どうしてもという必要があればやむを得ないが、一回当り〇・一ミリシーベルト(最近の胸部X線撮影で肺がうける被曝レベル)を越えるような作業はごめんこうむりたいと思っている。このような私流の感覚に基づくと、〇・〇〇一ミリシーベルトの被曝をめやすに、距離にして一・三㎞以内の人々は大なり小なりの被曝を受けてしまったと言えるであろう。
おわりに
私たちのグループ(原子力安全研究グループ)は、二〇年以上にわたって、原発で最悪の事故が起きたらとんでもないことになる、と警鐘をならし続けてきたつもりである。この間、一九七九年の米国スリーマイル島事故、一九八六年の旧ソ連チェルノブイリ事故と二つの大きな原発事故があった。次は日本の番かも知れないとは思いながらも、そんなとんでもないことは起きないようにと願ってきた。しかし、一九九五年のもんじゅナトリウム漏れ事故、一九九七年の東海村再処理工場爆発事故、そして今年のJCO臨界事故と、次第にスケールアップしながら国内原子力施設の事故が続いている。いずれの事故にも共通しているのは、事前にまったく予想もしていなかったようなきっかけから大事に至っていることである。
「原子力施設はどんなことが起きても大丈夫なように作られている」などと言ったらもはや世間のもの笑いであろう。しかし、JCO事故を通して見え隠れする日本の原子力開発の体質は、三〇年前からほとんど変わっていないように思える。原発で大事故が起きるかも知れないという私たちの警鐘が当たらないことを祈っている。原子力安全研究グループのこれまでの仕事や公開安全ゼミの内容についてはホームページ(http://www-j.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/)を参照願いたい。(いまなかてつじ・京都大学原子炉実験所)