Ⅰ.臨界事故の性質
夢にも思わなかった事故
「臨界事故…?」、まさか!
九月三〇日の昼、JCO燃料加工工場での臨界事故のニュースに接して、私は正直に言ってそうとしか思わなかった。おそらくは、ほとんどすべての原子力関係者はそう思ったと思う。ウランやプルトニウムなど核分裂性物質と呼ばれる物質は、一定の形状に一定量以上のそれが集まれば、物理学的な必然として核分裂の連鎖反応が始まる。核分裂の連鎖反応が持続的に起こるその状態を「臨界」と呼ぶ。連鎖反応を爆発的に進行させれば原爆となるし、制御できる状態で連鎖反応を進めさせれば、原子炉となる。そのことは、逆に言えば、一定の形状に一定量以上の核分裂性物質を集めなければ、決して「臨界」状態は起こらず、ウランは燃えない。燃料加工工場は、もちろんウランを燃やす工場ではないから、「臨界」状態など決して起こしてはならないし、そうすることも容易なことである。なぜなら、一定量以上のウランやプルトニウムが集まらないように工場内のすべての容器の大きさに制限を付けて起きさえすればよいからである。
日本では、国や原子力産業は「日本の原子力技術は優秀なので決して大事故は起こらない」と言い続けてきた。また、国が「厳密」な安全審査を行って大事故は決して起こらないことを確認しているとも言っててきた。私自身は、そうした国や原子力産業の主張を全く信用していなかったし、いつか原子力施設では人命にかかわる大事故が起こると言い続けてきた。しかし、その私にしても、核燃料加工工場で臨界事故が起こるなどとは夢にも思っていなかった。
日本の技術レベル
日本が欧米型の近代科学技術に接したのは、せいぜいこの一〇〇年ほどのことである。特に、原子力の場合は、第二次世界戦争で負けたために原子力研究そのものを禁じられ、理化学研究所のサイクロトロンなどごく基礎的な研究装置すらが、米軍によって破壊され、東京湾に沈められた。原子力研究が許されるようになったのは、一九五二年にサンフランシスコ講和条約が発効してからであるし、その後も、原子力と核が同じものであると洞察した学者の抵抗によって原子力研究は進まなかった。業を煮やした改進党代議士中曽根康弘が突如として二億三五〇〇万円(燃えるウランの質量数二三五をもじったもの)の原子力予算を国会に提出し、ろくな審議もしないまま成立してしまったのが、一九五四年三月のことであった。その年、すでにソ連では世界初のオブニンスク原子力発電所が運開を迎えていたし、米国でも一九五七年には商業用のシッピングポート原子力発電所が運開した。
遅れて原子力に参入した日本は、一九六六年になって東海一号炉を運転させるが、それは自分の技術で作ったのではなく、英国からコールダーホール型原子力発電所を輸入したものであった。その後、一九七〇年に敦賀一号炉、美浜一号炉を運開させるがそれらもまた自分の技術で作ったのではなく、米国から輸入したのであった。その後は、ほとんどの原子力技術は米国から導入することになり、ようやく今日に至ったが、今日でもなお炉心の中心部など核心技術はいまだに自立できないでいる。
その日本は、一九七九年に米国スリーマイル島原子力発電所で事故が起きた時にも、一九八六年の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所で事故が起こった時にも、「日本の原子力技術は優秀だし、日本人は優秀なので決して事故は起こらない」と言い放った。いつの時代も人の心には、慢心が住みつきやすい。自尊心をくすぐる宣伝は素早く人の心の奥深くに住みついてしまう。近代科学技術に関するかぎり、日本の技術レベルなどしれているが、原子力にいたっては、少なくても後進国である。私は、そのことを悪いことだとは言っていない。原子力技術は核技術そのものであり、本来手を着けるべきでない技術である。その技術の後進国であることはむしろ誇るべきことでもある。ただ、事実そのものは、価値判断を別にして、曇ない目で見るべきものである。過去に溶液系で起こった臨界事故の歴史と規模を図1に示す。核先進国でも開発初期に何度もの臨界事故を経験し、その苦い経験にたって、ごく特殊な例を除けば、すでに二〇年前に臨界事故は根絶した。それなのに、日本が原子力技術の先進国であるかのように慢心し、容易に防ぐことができるはずの臨界事故を引き起こした。欧米各国のマスメディアはこぞって、日本の原子力技術の未熟さを報道してきたが、けだし当然の指摘である。
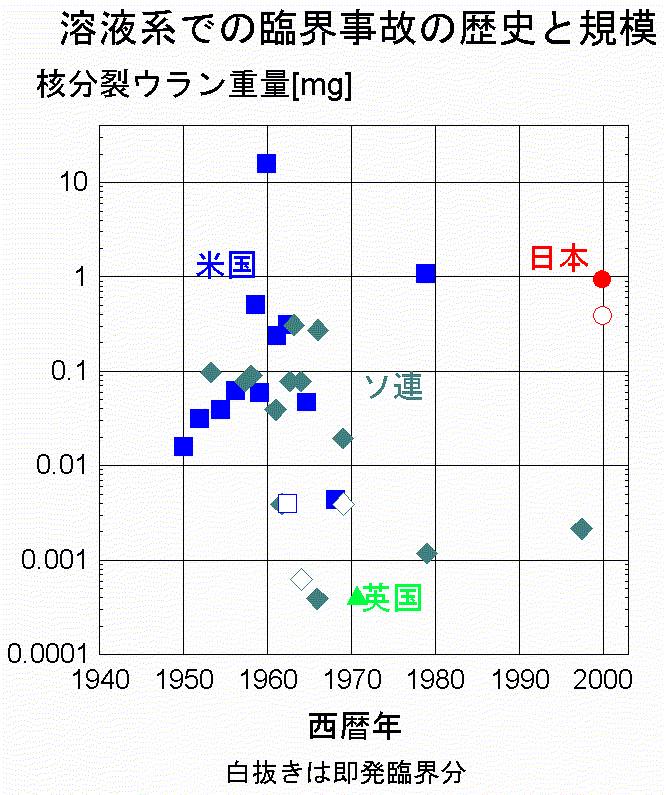 図1
図1裸の原子炉と放射線
ウランの核分裂が起これば、生じるものはエネルギー、放射線、放射能(正しくは核分裂生成物)の三者である。原爆では、これら三者がすべて有効な破壊行為として使われる。放出されたエネルギーは爆風や熱線となって街を破壊し、人々を焼き殺した。核分裂反応の瞬間に生み出される中性子線とガンマ線は爆心地周辺の住民に急性放射線障害を与えた。そして、きのこ雲に吹き上げられた放射能は黒い雨となって遠方の住民にも降り注ぎ、一部に急性の放射線障害を与え、残りの多くの人々を被爆者として、やがて現れるガンの恐怖に陥れた。
原子力の「平和」利用といわれる原子力発電所は、それら三者のうちエネルギーだけ、それもわずか三割だけを電気に変えて利用する装置である。残りの七割は廃熱として周辺環境に棄てる以外ない。(三〇年近く昔、「原子力発電とは生じるエネルギーの主要部分を廃熱として海に棄てる装置なのだから、原子力発電所という呼び方は正しくない。正しく言うのであれば、海暖め装置と呼ぶべきだ」と教えてくれたのは、今は亡き水戸厳さんであった。)その上、放射線と放射能はもともと厄介者でしかなく、厖大な鉄とコンクリートを使ってそれらを閉じこめ、厖大な安全装置を張り巡らせて、放射能の周辺への漏洩を防ごうとするのである。今回事故を起こしたJCOの燃料加工工場は、臨界事故は決して起きないと安全審査で保証された施設であり、それ故に核分裂の連鎖反応に対する備えは一切持っていなかった。そこには、中性子を検出するための測定器すらなかったし、中性子やガンマ線を遮蔽したり、放射能の漏洩を防ぐ安全装置もなかった。いわば「裸の原子炉」が突如として出現したのであった。
Ⅱ.放出された放射能
核分裂したウランの量
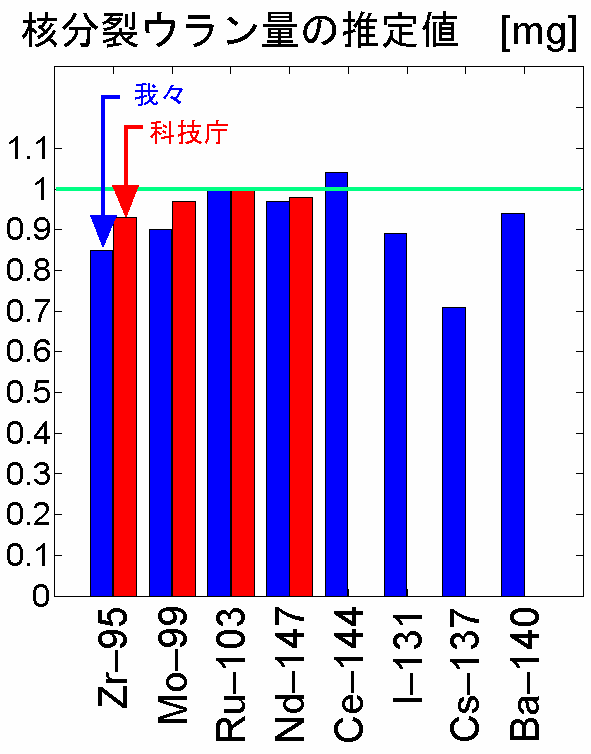 図2
図2
事故影響を考える上で、核分裂を起こしたウランの量を知ることは重要である。それを知る手がかりは二つある。一つは、周辺に漏洩してきた中性子線を直接あるいは間接的に測定・評価すること。もう一つは、核分裂の連鎖反応が起こった沈殿槽と呼ばれる容器の中に残っているウラン溶液を分析して評価する方法である。このうち前者については、すでに幾つかの評価が公表されているし、本号で今中さんが詳しく報告している。今中さんの評価によれば、核分裂したウランの量はおよそ〇.七ミリグラムである。一方、沈殿槽からのウラン溶液の採取は事故後二〇日たった一〇月二〇日に行われた(1)。ただし、生成された放射能の重量は極微量であるため、化学で言う「キャリア・フリー」状態にあり、容器壁に付着するなど複雑な挙動をとる。その上、採取する試料が槽内の溶液を代表していることを保証するためには、最低限、攪拌機が動かなければならなかったが、それは動かなかった。結局、採取された試料が生成した放射能の量を正しく教えてくれる保証はない。その点を充分に頭に入れた上で、核分裂したウランの量を評価してみると図2となる。評価に用いた放射能の種類によって若干のばらつきはあるが、およそ一ミリグラム程度であることが分かる。
そこで本稿では、一ミリグラムのウランが燃えたものとして、この後の議論を進める。その反応が放出したエネルギーの量は家庭で燃やす灯油に換算すれば、約二リッター程度のものでしかない。それが九月三〇日の一〇時三五分から一〇月一日の朝六時近くまでのおよそ二〇時間かけて沈殿槽内で燃えたのである。それでも、労働者と周辺住民に法令が許す限度をはるかに超える被曝を与えた。
希ガス
核分裂反応が起きれば、数百種類にのぼる核分裂生成物が生まれる。それらの中には、完全にガス体で、他のいかなる物質とも反応しない希ガスと呼ばれる一群の放射能がある。それらは生まれると同時にウラン溶液から沈殿槽内の空間に移り、その後、沈殿槽の開口部から施設内に、さらには施設の換気系によって建屋外に放出された。それらは、その時点での気象条件に従って、周辺に拡散し、住民に被曝を与えた。たとえば、周辺に配置されていたガンマ線用モニタリングポストの測定値の一例を図3に示す。
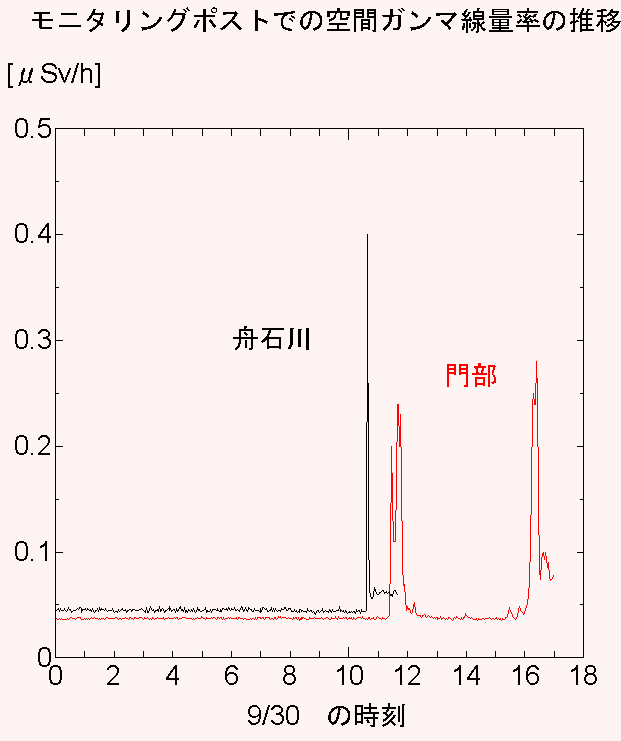 図3
図3JCO南約一.三キロメートルに位置した舟石川モニタリングポストでは、事故直後に、平常時の一〇倍に達するガンマ線を観測しているし、JCO西側八キロメートルに位置する門部のモニタリングポストは、事故発生から一時間後にまず第一回目の放射性雲に襲われた。この放射性雲の主成分は希ガスであったが、三〇分ほどで風向きが少し北向きに変わったため、夕方になって再び放射性雲に襲われるまで、しばしの平安をえた。科技庁の事故調査委員会に提出された資料(2)によれば、「日中の海風の時間帯では、計算によれば放射性雲は放出点西側の県のポスト(門部と磯部)の中間を通過したと考えられ、・・・」とされている。放射線を測定するモニタリングポストはまばらにしか配置されていない。しかし、住民はモニタリグポストがある場所にだけ住んでいるわけではない。放射性雲がモニタリングポストの中間を通過したということは、中間に住むんでいた住民たちを放射性雲が襲ったということである。
その後も希ガスを主成分とする放射性雲は風の向くままに周辺に流れた。一方、東海村は、国が一向に対応を示さないため、当日午後三時になって三五〇メートル圏の住民に避難要請を出した。住民たちはモニタリングポストがある舟石川コミュニティーセンターに避難させられた。ところが、夜になって風向きが変わり、図4に示すように、舟石川コミュニティーセンターはちょうど風下になって放射性雲に巻き込まれた。(3)
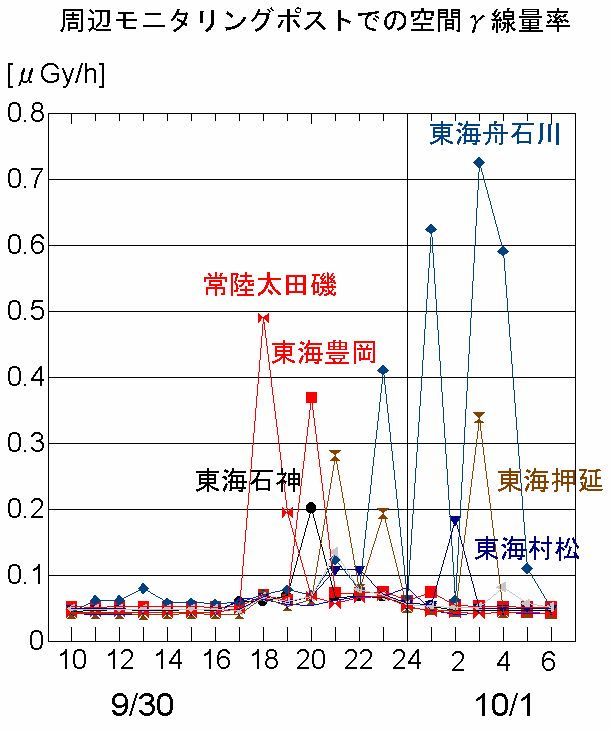 図4
図4ただし、希ガスが容易に環境に漏洩してきたのは、それが他の物質と全く反応しない性質を持っているからであり、それ故にまた、人体がそれを取り込んでもすぐに排泄されてしまって、内部被曝には寄与しない。したがって、住民が希ガスから被曝を受けるのは、放射性雲に巻き込まれているときだけであり、これらの図から読みとるかぎりは、住民の被曝量は多くても数マイクログレイである(ガンマ線の場合、一グレイ=一シーベルト)。また、科技庁による計算機シュミレーションによる評価でも、希ガスによる被曝は最大で五〇マイクロシーベルトとされている(2)。個人が天然の放射線から受ける被曝の量が年間一ミリシーベルトのオーダーであることを思えば、その数十分の一である。
ヨウ素
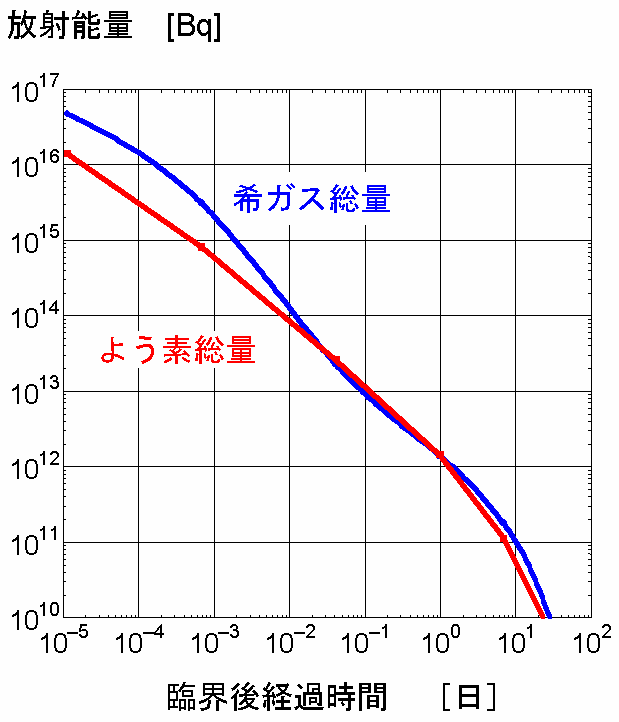 図5
図5
希ガスによる被曝量が少なかったとしても、安心してはいられない。なぜなら、生成された放射能の中には、希ガスより一層危険な放射能、ヨウ素があるからである。図5に示すように、核分裂によって希ガスとほぼ同じだけのヨウ素が生成される(4)。一九八六年四月に起こった旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故では、急性放射線障害が一段落した後に、小児の甲状腺ガンが多発した。それは事故で放出された放射性ヨウ素が引き起こしたものである。ヨウ素は、揮発性で環境に放出されやすい上、体内に取り込まれると甲状腺に集まる性質を持っている。
事故の報に接して以降、私は放射性ヨウ素汚染を何よりも心配した。東海村には日本原子力研究所(原研)、核燃料サイクル開発機構(核燃機構)など巨大な原子力関連研究機関があり、多数の専門家がいる。当然、事故直後からヨウ素測定が行なわれたはずだ。しかし、一日経っても二日経っても、ヨウ素についてのデータはいっこうに出てこなかった。業を煮やした私は、京大工学部の荻野晃也さんの協力を得て、自らヨウ素測定を行なうことにした。荻野さんが三日午前中に現地で採取したヨモギや土壌などの試料を四日に測定した結果、ヨウ素一三一、ヨウ素一三三の汚染を確認した。放射能や放射線には色もなければ、匂いもない。情報が与えられていれば避けえた被曝も、情報が与えられなければ避けようがない。この間、住民たちは一切の情報を与えられないまま被曝していたのであった。
その後、私の同僚の小林圭二さんが社会民主党の調査団としてJCO事業所内に立ち入り調査をしたが、そのときに採取した試料も含め、放射性ヨウ素汚染に関して今日までに公表されたデータを図6に示す。荻野さんと私のデータが公表されてからすぐ茨城県がほぼ同じ場所で、同じヨモギを採取して測定したが、放射能の減衰を補正すれば実質的に同じ結果となった(5)。その後、安全委員会の事故調査委員会に提出された資料には、すでに私たちの測定以前に原研が測定していたことも示されていた(6)。
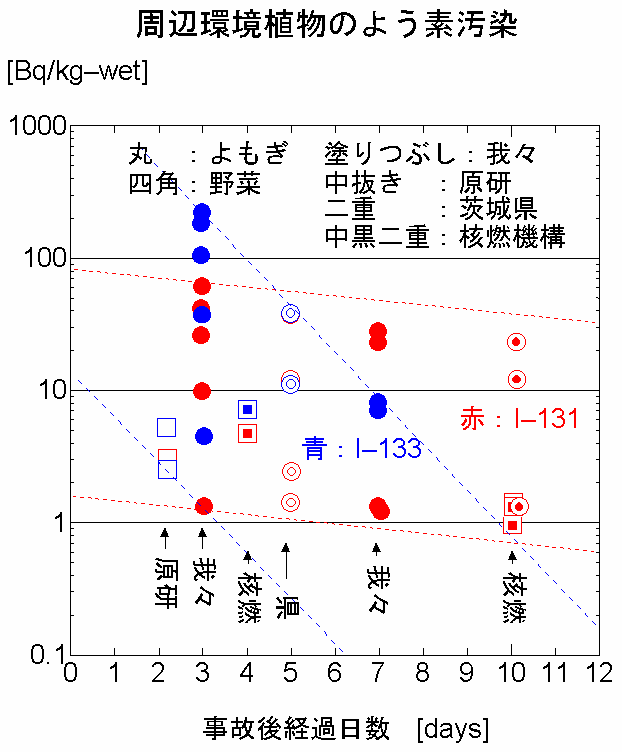 図6
図6
放射性ヨウ素が周辺環境に漏洩したのは、基本的にはJCOが臨界事故を想定していなかったからである。建屋の気密性に十分な配慮がなかったし、換気系にはヨウ素の捕集に有効な活性炭フィルタは設置されていなかった。その上、事故の最中も、その後も、換気系の運転が止められず、建屋内に漏洩してきた放射能はむしろ積極的に建屋外に放出され続けていたのであった。JCOは事故後八日後に、はじめて建屋排気筒でヨウ素測定をしたが、その時点でもなお周辺監視区域外へ放出が許される濃度の二倍を越えるヨウ素一三一が検出された(7)。その後、一〇月二一日までの測定データを図7に示すが、観測された減衰の傾向を単純にさかのぼっただけでも、事故当日には、濃度限度の一〇倍を越えるヨウ素が排気筒から放出されていたことになる。
国は測定された濃度は、排気筒のもので、敷地境界のものではないと言うであろうし、拡散計算を基に得られたヨウ素による被曝線量(全身換算の実効線量当量)は最大でも二四マイクロシーベルトであるといっている(2)。しかし、この値は、周辺に放出されたヨウ素の量を生成量の五%と仮定した値であるし、ヨウ素の化学系に依存する沈着速度などの誤差を考えれば、相当大きな誤差があると考えるべきものだ。そして、この場合も、換気系の停止、正確な情報の迅速な伝達がなされれば避け得たはずの被曝が、避けられなかった点に問題がある。
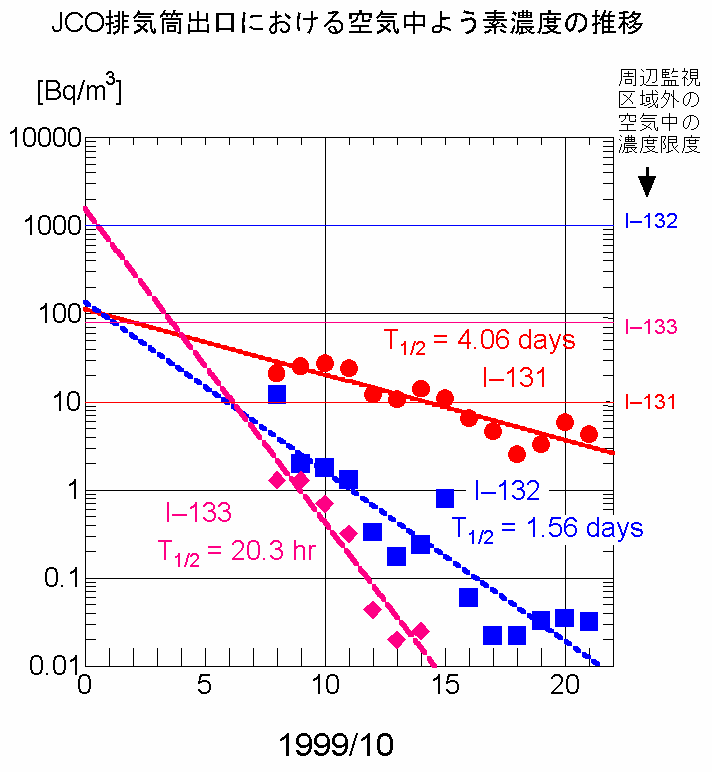 図7
図7
Ⅲ.多様な被曝
a.作業員
臨界事故時には三人の作業員が大量の被曝を受けた。その被曝量は、抹消リンパ球と血液中に生成されたナトリウム二四の測定値から、ガンマ線換算で、それぞれ一八(一〇~二〇以上)、一〇(六~一〇)、二.五(〇.七から四.五)グレイ当量と見積もられた(8)。従来の知見からすれば、ガンマ線換算でおよそ四グレイの被曝をすると、半数の人が死ぬ。八グレイも被曝すれば全員が死ぬと考えられてきた。グレイとは被曝した物体が放射線から受けるエネルギーの量を尺度にしており、一キログラム当たり一ジュールのエネルギーを吸収する時の被曝量が一グレイである。四グレイの被曝とは、人間の体温を一〇〇〇分の一度上げるだけのエネルギー量でしかないが、それでも被曝した半分の人が死に至る。生命体に対する放射線の効果がいかに過酷か理解できる。
現時点で三人の作業員はすべて生存しているが、最大の被曝を受けた作業員は、連日の大量の輸血にもかかわらず、症状はどんどん悪化していて、予断を許さない状態に陥っている。
b.事故収束作業に従事した労働者
今回の臨界事故は、はじめの即発臨界で沈殿槽が破壊されず、その後も臨界状態が長期間続いたことが特徴であった。周辺での中性子線量の測定値を見れば、臨界による出力は次第に減ってきており、いずれは自然に臨界状態が解消されたであろう。しかし、それがいつになるか予測できない状態では、危険を冒しても臨界を終わらせることは至上命令であったろう。結局、沈殿槽の周りの冷却水を抜いてみることになった。指揮に当たった原子力安全委員の判断で、その作業にはJCOの作業員があたることになり、まず将来子供を作る可能性のある若い労働者が除外された。また、作業に従事すれば、法令が定めている限度以上の被曝をすると予想されたため、業務命令で行なわせるわけにはいかず、あくまでも志願した労働者だけで行ったとされている。「志願」がどのような状況で、どのような一人ひとりの判断でなされたかを思うと、そのことだけで、一冊の本が書けるほどのドラマと苦悩があったであろう。
ともあれ、作業は実行された。作業に従事した作業員は、三人一組(一人は車の運転手)で数分毎の作業に従事したが、図8に示すように、放射線業務従事者の年間線量限度(五〇ミリシーベルト)を超えて被曝した人が一〇人近く、また、緊急時の限度として設定されていた一〇〇ミリシーベルトさえ超えて被曝してしまった人もいた(9)。
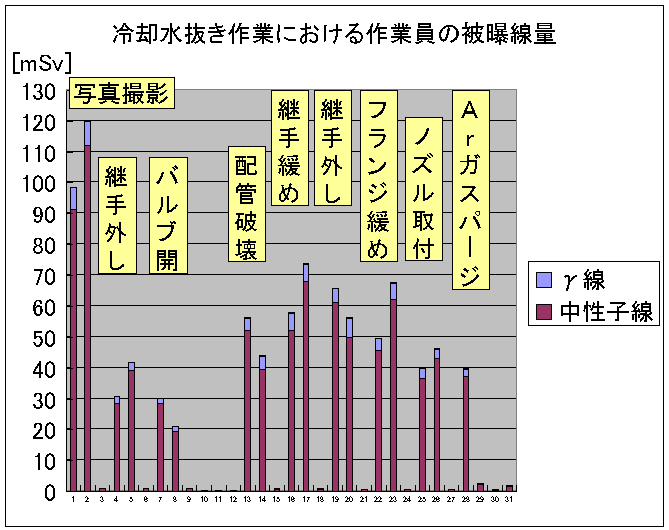 図8
図8
c.周辺住民
突然、裸の原子炉が出現した今回の事故では、核分裂反応で生じる中性子線とガンマ線が施設周辺に降り注いだ。臨界事故など起きないとの前提で操業許可がなされた施設には、もちろん中性子測定器すらがなく、当初は臨界が継続していることすら分からなかった。しかし、ガンマ線量率がいっこうに減らなかったため、JCOは事故発生から約三時間半後の一三時五六分、東海村に対して周辺住民を避難させてくれるように要請した。
これまで原子力には専門的な知識が必要だとして、一切の安全規制の権限を握ってきた国は、今回の事故でも一切の情報を独占した。ところが、情報を握るだけで、一切の対応をとらなかったため、東海村は苦悩のあげくに十五時になって三五〇メートル圏内の住民に避難要請を出す。しかし、後の解析によれば、すでにその時点までに三五〇メートル圏内の住民は一般公衆の年間線量限度である一ミリシーベルトを越えて被曝させられていた。
臨界自体はその後まだ一五時間にわたって継続したため、避難要請を受けず、家に残った三五〇メートル圏外の住民たちはその後も被曝を受け続けた。夕方になって、ガンマ線の十倍近い中性子線が出ていることが測定され、避難区域を広げなければならないことが認識されるが、その決断は「混乱が起きる」との理由で見送られてしまった。結局、図9に示すように、臨界が継続した全期間の被曝量を推定した結果によれば、半径五百メートル圏内の住民は法令の限度を超えて被曝した(10)。
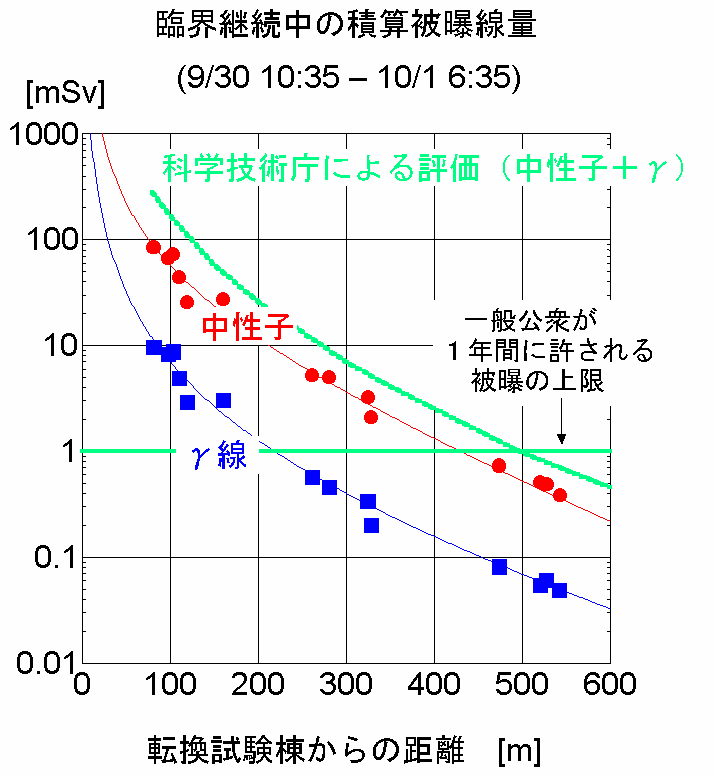 図9
図9
d.その他
繰り返しになるが、放射能や放射線には色もなければ匂いもない(厳密に言えば、放射性物質には色もあるし、匂いもある。しかし、色や匂いが感じられるようになるほどの量があれば、人間は生きていられない)。五感で感じられないものを相手にするためには、細心の注意を払って測定する以外にない。しかし、臨界事故を想定していなかったJCOには中性子測定器がもともとなかった。そのため、事故の実態を把握するまでに長い時間がかかってしまい、すでに本稿で取り上げた被曝以外にも、JCOの労働者、敷地境界外の住民、労働者などが被曝した。しかし、最近になって原子力安全局原子力安全課長が科学技術庁に出した資料(11)には、「がんの増加に代表される確率的影響も、一般的には実効線量で約二〇〇ミリシーベルト以上の線量でのみ現われるとされている。従って、今回の事故に関連しては、直ちにがんの増加などの健康影響を懸念する必要はないと考えられる」と記載され、行政としては被曝影響はとるに足らないという態度を鮮明にした。
いったい、この国の行政は何なのだと改めて思う。上の資料でも、「五〇ミリシーベルト以上の線量でも四〇年以上の後には、ごくわずかながらがんの増加が認められたという報告もある…」と書かれているが、広島・長崎の一〇万人に及ぶ原爆被爆者の多大な犠牲の上にようやくにして得られてきた疫学調査の結果は、五〇ミリシーベルト以下の線量ですら、ガンの増加を示唆し、そのデータが人類の被曝影響についての最大、最高のデータなのである。そして、観測できる最低レベルの線量まで影響は現われているし、さらに、図10に示すように、原爆被爆者のデータは低線量の方がむしろリスクが大きいことをさえ示している(12)。そうであるからこそ、日本の法令が依拠している国際放射線防護委員会の勧告でも、放射線はどんなに微量であっても影響があると認め、それゆえにこそ「確率的影響」という言葉を作ったのである。
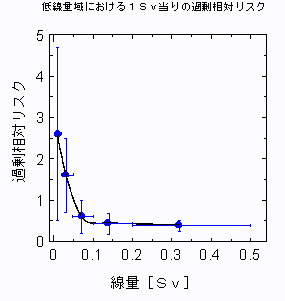 図10
図10
Ⅳ.国の姿と不可能な原子力防災
依らしむべし知らしむべからず
今回の事故に対して国がとった対応をみると、国というものの本質を見る思いがする。国はもともと住民を守る気などさらさらないということである。すでに述べたように、原子力の安全規制を一手に握ってきた国は、今回の事故に当たって、何の対応もとらなかった。やむなく、東海村が三五〇メートル圏内住民の避難要請、茨城県が一〇キロメートル圏内住民の屋内退避要請を出すが、なぜそうした措置が必要だったかの根拠は示されなかった。また、それらの要請は翌々日、翌日にそれぞれ解除されるが、そのときにもまた根拠は示されなかった。そのうえ、これもすでに述べたように、国はヨウ素による汚染を知りながら、一切の情報を公開しなかった。さらに、一〇月二日には農作物に関する「安全宣言」を出すが、これまた根拠は示されなかった。
また、中性子線の測定が始まり、臨界が継続していることが認識された九月三〇日夜には、避難範囲を三五〇メートルからせめて五〇〇メートルに拡大する必要があることも、緊急助言者組織内で議論されるが、そうした措置をとれば混乱が起きるとの理由で、見送られた。さらに、住民が避難した舟石川コミュニティーセンターがJCOからの風下に当たり、放射性雲に巻き込まれたことも認識され、住民を別の場所に避難させることも議論されたが、それもまた見送られる。
もともと不可能な原子力防災
表1にJCO事故に関連した行政当局の対応を一覧表にして示す。事故発生四〇分後にはJCOから科技庁に連絡が行っているが、科技庁の災害対策本部、政府の事故対策本部が作られたのは、それぞれ事故後四時間、四時間半経ってからであった。さらに安全委員会の中に専門家集団として緊急助言者組織を作ると決まるまでにはさらに時間がかかって、事故後五時間であった。おまけに、これらの組織が会合を開くまでにはさらにまた時間がかかり、緊急助言者組織の初会合が開かれたのは、事故後七時間半経ってからであった。その間、何の術もないまま放射線と放射能が労働者、住民を襲っていた。
| 表1 行政の事故対応 | |||
| 月日 | 時刻 | 経過
時間 |
対応 |
|
1999/9/30
|
10:35
|
00:00
|
事故発生 |
|
10:46
|
00:11
|
消防隊到着 | |
|
11:15
|
00:40
|
(国)JCO、科技庁に第一報 | |
|
11:34
|
00:59
|
(村)JCO、役場に通報 | |
|
11:35
|
01:00
|
(県)JCO、茨城県に第一報 | |
|
12:00
|
01:25
|
(警)対策本部 | |
|
12:10
|
01:35
|
(警)200m立ち入り規制 | |
|
12:15
|
01:40
|
(村)災害対策本部 | |
|
13:56
|
02:21
|
JCOが最大で500m圏の避難命令を村に要請 | |
|
14:30
|
03:55
|
(国)科技庁災害対策本部 | |
|
15:00
|
04:25
|
(村)350m圏避難要請 | |
|
15:00
|
04:25
|
(国)政府事故対策本部 | |
|
15:20
|
04:45
|
(警)3km立ち入り規制 | |
|
15:30
|
04:55
|
(国)原子力安全委員会、「緊急助言者組織」 | |
|
16:00
|
05:25
|
(県)事故対策本部 | |
|
16:51
|
06:16
|
(国)政府事故対策本部初会合 | |
|
17:45
|
07:10
|
(県)事故対策本部初会合 | |
|
17:55
|
07:20
|
中性子線の確認 | |
|
18:00
|
07:25
|
(国)安全委「助言者組織」初会合 | |
|
22:30
|
11:55
|
(県)10km圏の屋内退避要請 | |
|
10/1
|
6:15
|
19:40
|
臨界の収束確認 |
|
16:40
|
30:05
|
(県)10km圏の屋内退避要請解除 | |
|
10/2
|
18:30
|
55:55
|
(村)350m圏の避難要請解除 |
日本の原子力発電所が立地するにあたっては、安全審査を受けることになっている。その安全審査では、「重大事故」、「仮想事故」と呼ばれる事故が起きると仮定し、周辺の被曝線量が評価される。しかし、それらの事故は、いかにも最大限の事故であるかのように装われながら、実際には、炉心溶融は決して起きない事故でしかない。従来、炉心溶融が起こるような事故は、「想定不適当事故」という烙印を押されて、無視されてきたのであったが、そうした事故が起きないと断言できるわけではなく、最近になってようやく「シビア・アクシンデト」と言葉を換えて呼ばれるようになり、それへの対策を取ることが求められるようになった。仮に、そうした事故が発生するのであれば、環境への放射能放出は事故発生二時間後から三〇分の間に起こる。
原子炉とはもともと臨界状態を発生させるための装置であり、核分裂反応で生じる中性子線やガンマ線に対する防護措置を前提としている。一方、今回の事故は、JCOという燃料加工工場で起きた事故であり、もともと臨界状態wp想定していない場所での事故であった。そのため、労働者と住民の被曝の大部分は、反応で直接生じる中性子線とガンマ線によって引き起こされた。しかし、放射能(核分裂生成物)による被曝がなかったわけではない。ただ、燃料加工工場での臨界事故という性質上、今回のJCO事故で燃えたウランの量は、一ミリグラム程度でしかなかった。広島原爆で燃えたウランの量は七五〇グラムであり、それにくらべれば約一〇〇万分の一でしかない。ところが、今日では標準的になった一〇〇万キロワットの原子力発電所では、一年間に一〇〇〇キログラムのウランを燃やす。JCO事故に比べれば一〇億倍である。仮に、その九九%の閉じこめに成功したとしても、JCO事故の一〇〇〇万倍の放射能が環境に放出される。その原子力発電所で事故が起きてなお、住民が被曝から守られるなどと言うのであれば、もはやそれは信仰という以外にない。
【注】
- 安全委員会事故調査委員会十月二八日資料、【参考1】((株))ジェー・シー・オー東海事業所の事故の臨界反応の状況について、【別添資料1】日本原子力研究所、「ウラン溶液分析結果報告」、一九九九年十月二十七日
- 安全委員会事故調査委員会十月二八日資料、【参考2】(株)ジェー・シー・オー東海事業所の事故における周辺環境の線量評価について(理論的な基礎資料)
- 第五十九回原子力安全委員会資料第2-1号、事故調査対策本部、「((株))ジェー・シー・オー東海事業所において発生した事故による被ばく及び環境影響について(第1報)」、一九九九年十月七日
- 今中哲二氏の評価
- 茨城県生活環境部、「((株))JCO敷地境界付近の雑草からのヨウ素-131検出について」、一九九九年十月七日
- 安全委員会事故調査委員会資料3-3-1号、事故調査対策本部、((株))ジェー・シー・オー東海事業所の事故に係る環境モニタリングについて(実施状況)、一九九九年十月二十二日
- 安全委員会事故調査委員会資料3-10号、施設の処置の現状、一九九九年十月二十二日
- 安全委員会事故調査委員会十月二八日資料、【参考3】((株))ジェー・シー・オー東海事業所の事故におけるホールボディ・カウンタの測定結果に基づく被ばく線量の評価について
- JCO資料、「991001被ばく記録」
- 中性子線とガンマ線に分けて点を打って示した値は、(3)に示されている実測データを数学的に処理して、見積もった値で、事故初期の即発臨界バースト分は含んでいない。科技庁評価として示した線は、(2)で示されたもので、初期の二五分間のバーストが全体の四八%を閉めるとして評価されたもの。
- 原子力安全局原子力安全課長、広瀬研吉、「(株)ジェー・シー・オー東海事業所の事故に係る事故の状況と周辺環境への影響について」一九九九年十一月四日
-
馬淵晴彦、「保健物理」、第三二巻、第一号、頁五~八(一九九七)