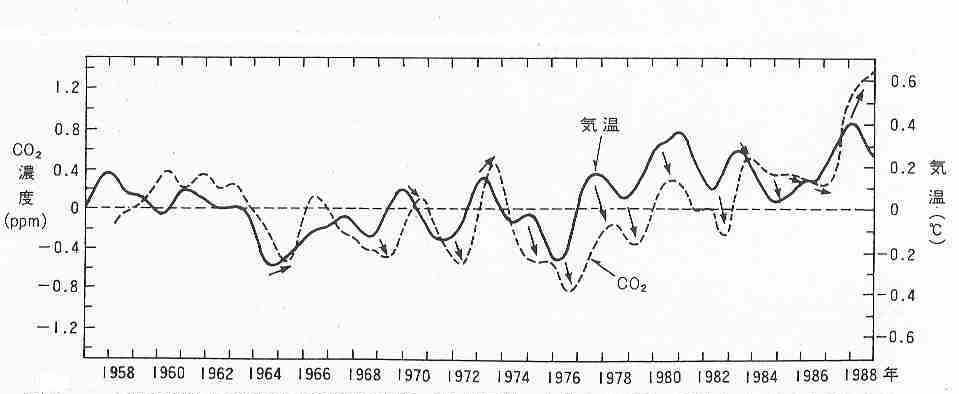
CO2温暖化脅威説は世紀の暴論
-寒冷化と経済行為による森林と農地の喪失こそ大問題-
1998.12.22 名城大学商学部 槌田 敦
要約
CO2温暖化脅威説は、その成立条件を検討しないまま、多くの人々が信じこんでしまった。これについて、11の事実を挙げて反論する。O3ホールのフロン原因説が正しくないことも指摘する。
20年前に消えてしまった寒冷化説の提起した問題点を掘り起こし、この寒冷化に耐えられる経済構造を確立するための議論が必要であることを述べる。
また、CO2温暖化脅威説や京都議定書を受けて提案されている太陽光や原発などの取り組みが、石油を大量消費し無意味であることを示す。
そのうえで、穀物の過剰生産と自由貿易と債務返済による農地と森林の喪失がもっとも大きな環境問題であることを説明する。この問題が、CO2温暖化脅威説の陰に追いやられ、議論できない状態にされている。このままでは、間もなく予想される寒冷化と重なり、世界的な食料不足の心配がある。
農地と森林の喪失を引き起こした経済行為について考える人々が少しでも多くなることを願い、あえて思うままを話す。
序論
CO2温暖化脅威説は、たとえば南極ボストーク基地における氷床の調査により、大気中のCO2濃度と気温とが過去22万年にわたって関係があることなどを根拠にしている。しかし、ふたつの現象が長期にわたって関係する時、どちらが原因でどちらが結果なのか。または別に本質的な原因があって、この両者は共にその結果なのか。その考察をすることなく、人々はCO2濃度上昇で気温が上ると信じ、その対策を一大国際政治課題にしてしまった。
これにより、寒冷化説をとり続ける地道な学者は、研究費が得られず、また研究してもこれを発表する場をレフェリー制度によって奪われ、さらに圧倒的に多い温暖化論者の前に意欲を失い、沈黙を余儀なくさせられたように見える。寒冷化説の指摘した問題点は、現在もなお有効である。
ここでは、CO2温暖化脅威説やO3ホールのフロン原因説が間違っており、また京都議定書を受けて提案される太陽光や原発などの取り組みが無意味であることを示す。さらに、過剰生産、貿易、債務という経済行為を原因とする農地と森林の喪失がこのCO2温暖化説の陰に埋没しているという現実を打破するため、あえて思うままを率直に話すことにした。
【気温の変化がCO2濃度の変化に先行する】
多くの研究者は、大気中のCO2濃度の増大が気温を上昇させると言う。しかし、事実は逆である。ハワイのマウナロア観測所でのCO2の長期観測者として知られるC.D.Keeling グループの研究によれば、図1に示すように、気温の上がった半年~1年後にCO2が増えている1)。(事実①)
図1 気温の変化と二酸化炭素の変化の対応
(CO2は気温の上昇より遅れて変化していることがわかる.)
また、C.D.Keelingらは、エルニーニョ発生の1年後にCO2が増えたことも発表した1,2)。赤道付近の海面温度の上昇がCO2濃度の上昇の原因となっているのである。 (事実②)
したがって、大気中のCO2濃度の増加で温暖化するのではなく、気温(海面温度)の上昇でCO2濃度が増えるというべきである。根本順吉は、このC.D.Keelingらの仕事に注目し、「現在の温暖化のすべてを温室効果ガスによって説明することはたいへん無理である」と述べた3)。しかし、このC.D.Keelingらの研究も、根本氏の見解も無視されたまま、現在に至っている。
【南半球大気中のCO2濃度の季節変化】
人間の発生したCO2が大気中に溜まるとする説の論拠は、海洋の表層水は10~20℃で軽く、深海水は0~5℃で重いから、これらの海水は混合しない。また、表層水のCO2溶解量は少ないから、大気と表層水との間でCO2交換があってもその量は少なく、大気中のCO2濃度に深海水のCO2が影響することはない、という考え方に基づいている。
しかし、それでは北半球で大気中のCO2濃度に10ppm程度の季節変化があるが、南半球でほとんど季節変化がないという周知の事実を説明できない。 (事実③)
北半球と南半球の違いは海と陸の面積の違いである。北半球(30゚N~70゚N)では海と陸の面積はほぼ等しいが、南半球(30゚S~70゚S)では海は90%以上を占めている。その南半球で、夏、表層水で植物プランクトンが活発に光合成するが、大気中のCO2を必要としていない。
表層水での光合成に必要なCO2は深海水から供給される以外には考えられないから、表層水と深海水の間にCO2のやり取りがないとする説は正しくないことを示している。
【両半球大気中のO2濃度の季節変化】
R.F.Keelingらは、大気中のO2度が北半球でも南半球でも季節変化していると発表した4)。海の生物にとって、表層水に溶けているO2だけでは不足し、またCO2と違って深海からのO2の供給は考えられないので、大気中のO2が必要なのである。 (事実④)
ここで、大気中のO2とCO2濃度を合計すると、生物の光合成や呼吸の効果を消去できる。R.F.Keelingらによれば、この合計の季節変化は、北半球、南半球とも、生物効果とほぼ同じ大きさである。 (事実⑤)
このO2とCO2の濃度の合計の季節変化は主に、海洋と大気の間のこれらの気体の交換の結果である。夏には海洋から大気へ、冬には大気から海洋へこれらの気体が移動している。海洋と大気の間で気体の移動は少ないとすることが間違いであることが分かる。
【海洋での炭素循環】
深海水との関連で表層水のCO2濃度を論ずるには、海洋における炭素の全体の流れを考える必要がある。それは海洋の炭素の上下循環で決まる5)。
表層水への炭素の供給は炭素濃度の高い深海水の湧昇でなされている。赤道で貿易風が吹くと、西向きの海流が生ずるがこの東端で深海水が湧昇する。太平洋ではペルー沖である。中緯度で赤道に向かう風が吹くと赤道に向かう海流が生ずるが、これは地球の自転についていけず、西向きに方向を変える。この海流と大陸西海岸との間に透き間ができるが、ここで深海水が湧昇する。太平洋ではカリフォルニア沖とチリ沖である。また極洋では、冬に表層水の温度は氷点の-2℃になる。この温度の海水は最大密度であり、また氷結によって塩分濃度も増えるため重くなって沈降し、代わりに0~3℃の軽い深海水の湧昇となる。
この深海からの湧昇水は炭素化合物とリンや窒素などの養分が豊富である。表層水に供給された炭素化合物は細菌などの餌となり、大気から供給されるO2によってたちどころに酸化されCO2になる。この豊富なCO2と養分によって海洋の光合成が進行し、この湧昇海域は漁場となる。
ここで生育した海洋生物は、世界の海に拡散し、海洋動物の餌となり、結局は糞になる。糞は海水より重いので沈降し、炭素と養分は深海に帰っていく。つまり、表層水のCO2濃度は深海水の湧昇と糞の沈降で決まることになる。
植物プランクトンの元素構成比(Redfield比)はC:N:P=106:16:1であるが、深海の元素構成比もこれとほとんど同じであるから、湧昇海域では、光合成に必要な養分濃度とCO2濃度は過不足なく均衡している。したがって、南半球の光合成にとって大気のCO2は必要がなく、その濃度は季節変化しないのである。
【気温を決めるのは太陽光と地球の受光能】
このように、大気中のCO2濃度はヘンリーの法則により海洋表層水の温度とそのCO2濃度で決定される。表層水の温度は太陽活動と地球の受光能で決まる。
太陽活動の大きさは黒点の数と対応している。黒点の数の変化と気温の変化は直接関係し、CO2の変化はこれに遅れて続くという事実も報告されている1)。 (事実⑥)
また、図2に示すように、北極圏では、過去350年にわたる気温の変化と太陽光の受光量の変化はよく対応している6)。 (事実⑦)
図2 北極圏における気温、CO2濃度、照射量の比較
さらに、1992年から2年間、人間がCO2の放出をやめたわけではないのに、大気中のCO2濃度はまったく増えていない。CO2温暖化説によれば、このCO2は完全に行方不明ということになる。 (事実⑧)
この原因は1991年のピナツボ火山の噴火により、微粒子が成層圏に放出され、地表の受ける太陽光が減ったからである。
これらの事実によって、大気中のCO2濃度は人間の発生するCO2によって決まるのではなかったことが分かる。そもそも、人間社会の発生したCO2が大気中に溜まるとすると、その半分が行方不明になるという欠陥は20年も以前から指摘されていた。これを放置したまま、CO2温暖化説を信じたことに間違があった。
【温暖化ガスとしてのCO2の効果】
以上述べたように、気温の上昇で大気中のCO2濃度が上昇する。しかし、そのCO2が気温を上昇させる効果も二次効果としては無視できない。ところで、温暖化ガスの中でもっとも影響の大きい気体はH2Oである。多くの議論ではこのことが無視されている。
熱帯または温帯の夏、大気中のH2Oの量が多いので、CO2が多少増えたところでCO2による影響はない。しかし、寒帯または温帯の冬、大気中のH2Oの量は少ないので、地表から放出される遠赤外線は宇宙にそのまま逃げていく。これはいわゆる放射冷却である。ここで、大気中のCO2濃度が増えるとこの放射冷却は妨害され、地表は保温されることになる。 (事実⑨)
これは温室での保温効果ではない。地球の温室効果は他に実在し、重力が原因である。これにより窒素や酸素は地球から抜け出せず大気を作っている。この大気がなければ地表の温度はマイナス18℃以下となる。CO2による温暖化効果を温室効果(greenhouse effect)と呼びつづけることは大きな間違いをそのままにすることである。
H2OやCO2の温暖化効果は、これらの分子が遠赤外線を吸収し、また放出する能力によって生じる。この温暖化効果は、真綿を被ると空気の出入りが自由であるのに、暖かい効果が得られるのと同じである。したがって、このH2OやCO2の温暖化効果は、真綿効果(silk effect)とでも呼ぶべきであろう。
このCO2の二次的な保温効果によって、寒帯または温帯の冬は暖かくなるが、この温暖化は、地球上の生命にとって悪い効果をもたらしたことはない。
5千年以前の古代文明(日本では縄文文明)や1千年前のノルマンの侵略(日本では平安末期)以前の気温の高かった時代を、気象学者は、ヒプシサーマル(気候最適期)と呼び、人類にとって高温時代は暮らし易いと判断していたのである。
【地球寒冷化の心配】
逆に、気温が低い時代は人類は不幸であった。その理由は、陸の光合成は気温が15℃以上でなければならないからである。 (事実⑩)
現在、平均気温が15℃ということは、陸地の半分で光合成ができないことを意味する。これが低温になると、この面積が増えて、食料が得られなくなる。
1950年代、暖冬続きで地球の温暖化が問題になった。そのころ南極の氷がとけて海面が上昇し、大都会が水没するおそれがあると騒がれた。ところが、1970年代に入り、気温が上がらず、地球寒冷化が問題となった。実は、1940年以後、気温は徐々に下がっていることが確かめられた。そこで気象学者の多くは1980年ごろから、寒冬・冷夏がふえ、小氷河期の気候に近づくと予想した7)。
図3は、過去2万年の花粉、樹相、氷河からまとめた気温の変化(連邦研究協議会記録、1975)である8)。これによれば、7千年前に高温期があり、それ以後長期低下傾向にある。とくに注意すべきは、その間に3回、約2000年の間隔で、約2℃の温度降下をもたらす小氷期がある。
図3 過去2万5千年間の北半球の気温の変化
前回の最高気温期が2千年前であるから、現在が最高気温であり、間もなく気温が下がっていくとした1970年ころの気象学者の予想はやはり正しいのである。
蛇足であるが、世論に迎合して寒ければ寒冷化説を主張し、暖かくなれば変更の理由も示さず温暖化説を唱えるような、最近の学者の生態には、わたしはとてもついていけない。
【大気汚染による寒冷化と温暖化】
人間による地球気候への影響について、もっとも考慮すべきは、CO2ではなく、大気汚染である。
地球を開放系の熱学の対象とするとき、重要な事項は入力としての太陽光の受光状態、出力としての宇宙への放熱状態、そして地球に存在する物質循環の3点である9)。
まず、太陽光を15℃の地表で受ける。次に、対流圏上空のマイナス23℃で宇宙に放熱する。これによって、下が熱せられ、上が冷やさせるので対流圏の大気の循環活動が成立する。まさに地球エンジンである。この大気の循環が、地表の水と大気中の水蒸気の間の循環活動を作る。つまり、地球は空冷と水冷の機能をもつことになる。この大気と水の循環は海水の上下循環活動を発生させ、また養分の循環を作って生態系を成立させている。つまり、大気の循環こそが地球での諸現象の根源である。
そこで、この大気の循環を阻害する人間活動を考える。それは、大気汚染である。まず、可視光と赤外線に対して汚染物質が白い場合、太陽光は宇宙に散乱されるから気温を降下させる。
大気汚染が、可視光と赤外線に対して黒くて、成層圏にある場合、太陽光は吸収されて成層圏の温度は上がるが、この熱はそのまま宇宙へ放熱され、対流圏の大気循環に対してはほとんど影響がない。しかし、この汚染は地表に届く太陽光を少なくするので、白い汚染と同様に寒冷化をもたらすことになる。
黒い汚染物質が対流圏に放出される場合は、深刻な影響を受ける。太陽光はこの汚染物質に吸収されてその高度の大気を加熱する。そして、地表に到達する太陽光は減少する。その結果、上が加熱され、下が減熱されることになるので、大気の循環は阻害され、地表は熱平衡に近づく。また、大気循環が滞るため、風が吹かず、水があっても蒸発しない。地球の持つ空冷と水冷の機能を損なうことになる。これは温暖化というよりも、熱地獄である。 (事実⑪)
この現象は都市気象(ヒートアイランド)として知られるが、これが世界各地に広がっている。インドネシアやブラジルの焼畑を原因とする熱帯林の火災による煙は、赤道上空を覆い、貿易風や積乱雲の発生を妨害して、赤道海面の温度を上げる原因となった。また、北極圏では、工場や航空機の黒い煙による対流圏大気の汚染がある。これは北極圏の気温上昇の一因である。
以上述べたように、CO2温暖化脅威説は11の事実から否定される。CO2温暖化脅威説は、まず人間の活動を考えた。しかし、人間の活動はまだ地球全体に及ぼすほど大きくはない。したがって、より根源的な事象としてまず太陽活動、ついで地球の受光能、そして人間活動の地域に及ぼす影響の順に考えることである。これを逆にすれば矛盾した結果になるのは当然である。
【無意味な温暖化対策】
CO2温暖化脅威論がナンセンスである以上、この脅威を防ぐためのCO2対策もナンセンスということになる。もしも、文明批判が目的であれば、結果として発生するCO2を論ずるのではなく、石油など資源の大量使用を直接論ずるべきである。
それだけでなく、提案された対策の多くは発生するCO2を減らすことにもなっていない。これらの対策は、ほとんどすべてコスト高である。コスト高ということは、間接的に石油や石炭などを大量に消費することを意味する。
たとえば、太陽光発電の場合、半導体や関連機器の生産や設置に巨大な費用が必要だが、それは石油の消費でなされている。つまり、余計にCO2を放出することになっている。
ここで、エネルギーまたは物質収支の計算がなされるが、この種の計算の最大の欠点は積み上げ方式をとっていることである。このため、入力の積み上げを忘れても、出力損失の積み上げを忘れても、効果は良い方に傾き、提案者に誤った希望を与えることになる。
【原子力発電ではCO2排出量も減らない】
このことは、とくに、原子力発電の推進根拠の失敗に現れている。原子力発電所には、小さな重油タンクがあるだけだから、発電時にはCO2をほとんど出さないと説明される。しかし、この発電時以外のところで大量のエネルギーが投入されており、原子力発電はCO2を大量に発生している。
アメリカのエネルギー開発庁(ERDA)が1976年に計算したところによれば、エネルギー産出量100を得るために26のエネルギーを投入している。産出投入比は100/26=3.8である。電力中央研究所による1991年の計算も4.0とほとんど変わらない。
この結果は原発が有利なように見える。しかし、これは積み上げ計算であるから、積み残しを考慮していくと、投入量は増え、産出量は減り、結果として産出投入比はどんどん減ることになる。
ERDAの場合も、電中研の場合も、運転での電力投入(7)、遠方送電の建設(5)、揚水発電所の建設(10)という投入が忘れられている。これを考慮すると、投入量は26+7+5+10=48となる。また遠方送電損失(7)、揚水発電損失(20)という欠損があり、産出量は100-7-20=73となる。その結果、産出投入比は73/48=1.5となる10)。
さらに、計算不可能な投入として、放射能対策、廃炉対策、事故・故障対策がある。これを評価すれば、産出投入比は1に近づき、そして1を割ることになっていく。原発は事故で庶民を加害し、また処理処分不可能な放射能を残すだけでなく、石油石炭を大量に消費するのである。
現代の温暖化キャンペーンは、このような原子力をCO2削減のエースとして推進するためであった。アルゼンチンで開催された気候変動枠組み条約第4回締結国会議(COP4)は、さながら原子力発電の売り込みの場であったと伝えられている。これに誘導されて大騒ぎするなどまったくナンセンスとしか言いようがない。
【ナンセンスといえばオゾンホールも】
通説では、フロンから塩素が出て化学反応で成層圏のオゾンを壊し、南極にオゾンホールが広がり、地表に届く紫外線が増え、皮膚ガンが増えると心配されている。
オゾンを壊すという化学反応には、塩素の他に紫外線が必要である。しかし、南極の春先、太陽光は水平に入ってくるので、光が通過する大気の厚さは、真上から入射したときの10倍にもなる。そのため、紫外線は南極の上空に届く前に宇宙に散乱され、ほとんど存在しない。これではオゾン破壊になるわけがない。
フロンがオゾン層を破壊するという説の論拠は、南極の高層成層圏では強い西風が吹き、その極渦がエアカーテンとなって南極の大気を隔離する。オゾンの出入りがないのにオゾンが減るのだから、ここでオゾンが破壊されているとしなければならない、と。しかし、ほんとうに南極の大気は閉ざされているのだろうか。
高層成層圏での強い西風の原因は地球の自転である。地球が西から東へ動いているため、大気も一緒に西から東へ動いている。赤道の大気はもっとも早く動いており、南極の大気はあまり動かない。
ここで、赤道の大気が南極に向かって移動すると、地球表面の速度は、南極に近づくにしたがって遅くなるので、大気の方が早く動くことになる。つまり、緯度が高くなる方向に大気が動くと、西風になる。
南極の周辺で高層成層圏に強い西風が吹いているということは赤道から南極の方向に向けて大気が流れていることを示している。高層成層圏の西風はエアカーテンではなかったのである。
南極に流れこむ高層成層圏の大気にはオゾンが1/10と少ない。したがって、南極のオゾンが減るのは当たり前である5)。この南極成層圏の西風という事実だけからフロン原因説は覆されてしまった。
そのうえ、オゾンは紫外線が存在すると大気中の酸素から直ちに生産され、蓄積される。したがって、太陽光の有害紫外線はそれほど気にする問題ではもともとなかったのである。
【森林と農地の喪失こそ最大の環境問題】
現状では、環境問題はCO2温暖化とO3ホールの話題がほとんど独占している。しかし、最大の環境問題は、農地と森林の喪失である。この原因は、過剰農業、過剰放牧、過剰伐採といわれているが、そもそもなぜ過剰になるのか、ということの議論が欠けては、対応できるわけがない。
まず、科学技術はアメリカなど先進国で穀物の過剰生産をひき起こし、穀物の価格を下げてしまった。その結果、まだ穀物を生産できる農地であっても、採算がとれなくなって放棄されている。この放棄された農地は風水害で荒地となり、砂漠化している。
また、先進国での穀物価格の低下は、農民を離農させ、失業問題となった。そこで農民の失業を抑止するため、この過剰穀物は輸出している。
農産物の代表的輸出国アメリカの穀物生産量は、人口を養う約5倍という。そのうち1は国民が食べ、3は家畜の餌にし、残りの1を輸出している。これは補助金をつけて、さらに安い価格で輸出されている。また援助物資という形で輸出される穀物も、実は失業対策であった。
1994年の世界の小麦の貿易量は9900万トンであった。その輸出国の筆頭はアメリカ(31%)で、これにカナダ(22%)、オーストラリア(13%)、フランス(13%)、ドイツ(6%)、アルゼンチン(5%)、イギリス(4%)が続く。これらの国だけで小麦の輸出量のほとんどすべてになっている。
これらの先進国の穀物の輸出攻勢を受けて、途上国の穀物生産は壊滅状態になった。とくに、アフリカの場合、昔は小麦を食べなかったが、たびたびの飢饉の際、援助物資の小麦で食の嗜好が変わり、都会の住人に小麦を食べる習慣ができてしまった。
そうなると農家がミレット(きび)などの雑穀を生産しても、都市の住民は買ってくれない。やむなく農業を放棄して、都市のスラムの住民になる。先進国の失業対策は、途上国への失業の輸出を意味している。そして、放棄された農地は、風水害によって荒地となり、砂漠化することになる。
先進国の科学技術による穀物の生産性の向上は、世界の人々を飢えから解放すると期待された。しかし、事実は逆で、先進国でも途上国でも有用な農地を砂漠化し、将来の飢えの原因を作っている。
【債務返還と利子払いが途上国の農地破壊を加速】
砂漠化には、植民地から独立国になったことによる政治問題も関係する。植民地時代、植民地政府は綿花やコーヒーを栽培させた。それでも、農民を永続的に働かせるため、穀物生産のための農地は保護していた。
ところが、独立で状況は一変する。独立した政府に、先進諸国から多大な資本の貸付が行われた。ところが、1982年以降、債務の返還と利息の支払いで、資金は一方的に途上国から先進国へ流れることになった。
世界の富は貧しい国から豊かな国へ流れている。途上国ではこの債務や利息の支払いのために、穀物生産をやめて換金作物を作っている。しかし、多くの途上国ではコーヒーなど換金作物を売った額の半分近くをこの返済に当てている。
このような無理をして換金作物を作っているため、農地は荒れる一方で、ますます途上国の砂漠化が進むことになる。
【途上国における森林破壊】
途上国の農民が都市のスラムへ行かないで農業を続けようとすれば、まだ肥沃な土地のある森を焼き、開墾すればなんとかなる。しかし、そのようにして得た農地は2、3年で養分がなくなるのでそこを捨てて、また別の森林を焼くことになる。
日本へ輸出する木材の過剰伐採も森林を破壊する原因であるが、それ以上に焼畑の方が深刻である。スマトラ島のように、焼畑の火が森林火災の原因となって森を大規模に失うこともある。放牧でも森を焼いている。このようにして利用した森林の跡地はすべて砂漠化している。
このように、砂漠化を進めているのは、穀物の過剰生産と穀物の自由貿易と債務である11)。これを止めるのは容易ではない。よほど議論して対策を立てなければ、良い結果は生まれない。
ともかく、このままでは、世界中で農地と森林を失い、農耕できない荒れ地ばかりにするのは確実である。このときに地球寒冷化と異常気象が襲うであろう。われわれがこの現象をなすすべなく見逃したばかりに、子孫は苦しむことになる。
このような農地と森林の破壊こそ大問題であるのに、炭酸ガス温暖化脅威説振り回され、世界各地の環境悪化の経済的原因を十分に議論する機会が奪われていることは、残念というほかはない。
【環境問題を正しく理解するには、開放系の熱学が必要】
生命は、なぜ、その活動を維持できるのか。この問題の答えは、開放系の熱学を学ぶことによって得られる9)。いわゆる、エンジンの理論である。地球環境はこのエンジンの法則の範囲の中にあるから、これらの問題を議論するにはこの開放系の熱学が必要不可欠である。
また、人間社会もこのエンジンの法則により維持されている。このエンジンは、需要があれば供給すると儲かるという欲望の法則によって動いている。これを無視して環境問題や人間社会を論ずると、CO2温暖化やO3ホールだけでなく、中途半端な議論に明け暮れ、その結果は、大気汚染や自由貿易や原発など本質的な環境破壊行為を見逃し、これをますます悪い方向に広げることになる11)。現状は残念ながらそのとおりである。
(京都大学原子炉実験所での講演記録・1998.12.22)
1) Keeling,C.D.et al. Aspects of Climate Variability in the Pacific and the Western Americas (ed.Peterson,D.H.)pp.165-236 (Geophys. Monogr.55, Am. Geophys.Union, Washington DC,1989)
2) Keeling,C.D.et al.Nature 375 668 (1995).
3) 根本順吉 『超異常気象』 中公新書 (1994年)
4) Keeling,R.F.et al.Nature 358 723(1992),Nature 381 218(1996).
5) 槌田敦 『地球は興味深い熱学系』 日本物理学会誌 53巻p616(1998).
6) Overpeck,J.et al.Science 278 1251(1997).
7) 朝倉正 『異常気象と環境汚染』 NHKブックス(1972年)
8) R.A.ブライソン、T.J.ムーレイ 『飢えを呼ぶ気候』 根本順吉、見角鋭二訳、古今書院(1976)
9) 槌田敦 『熱学外論-生命・環境を含む開放系の熱理論-』 朝倉書店 (1992年).
10) 内山洋司、槌田敦、石谷久 エコノミスト 92年11月17日号 p67.
11) 槌田敦 『エコロジー神話の功罪』 ほたる出版 (1998年)