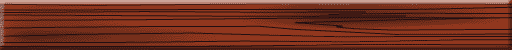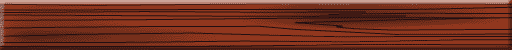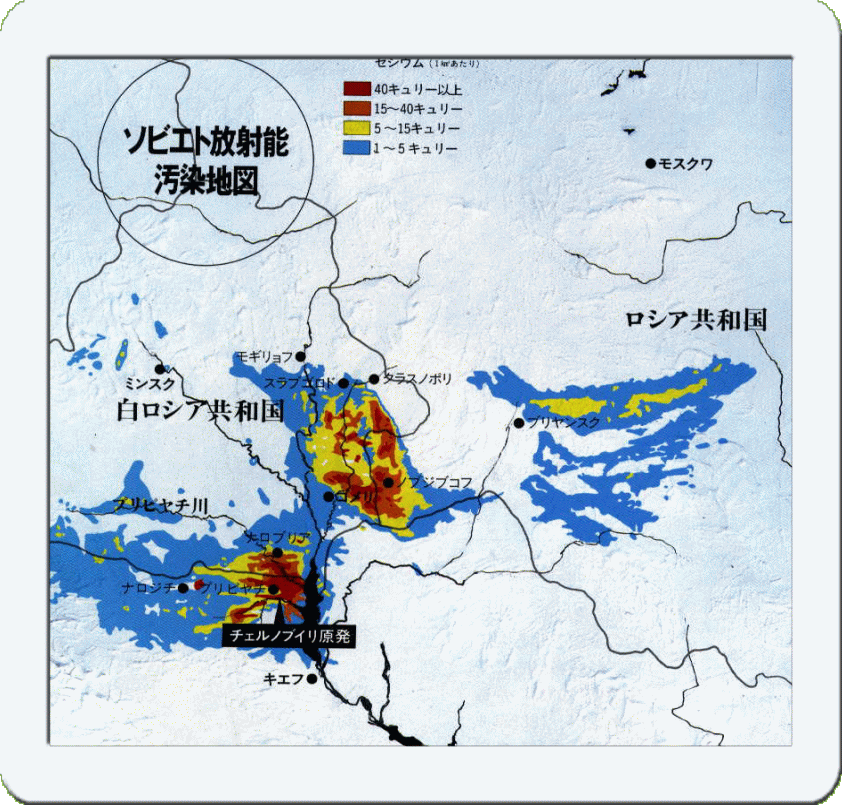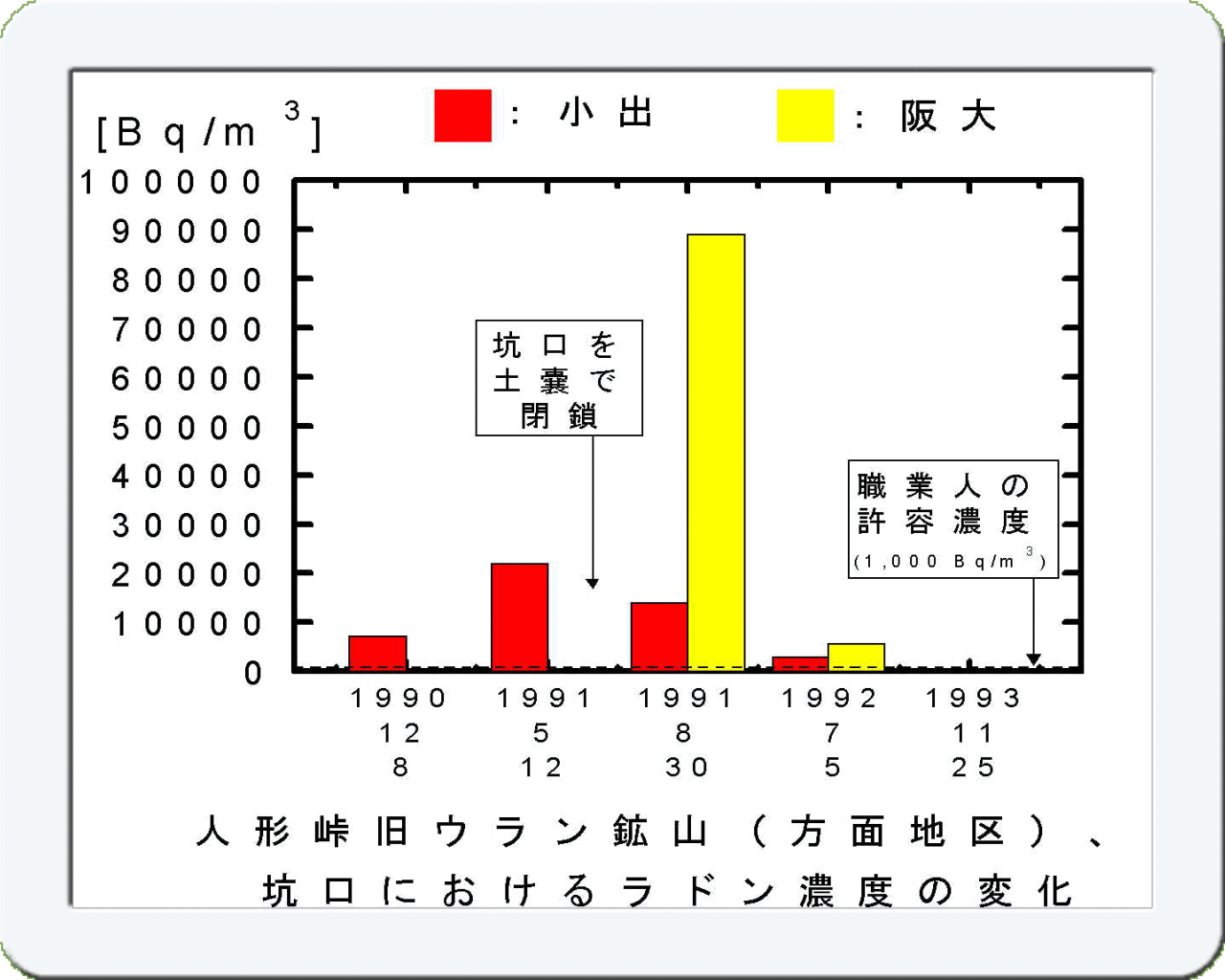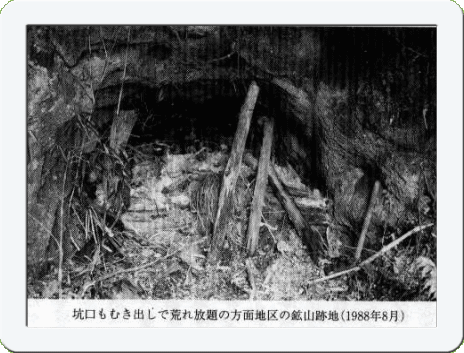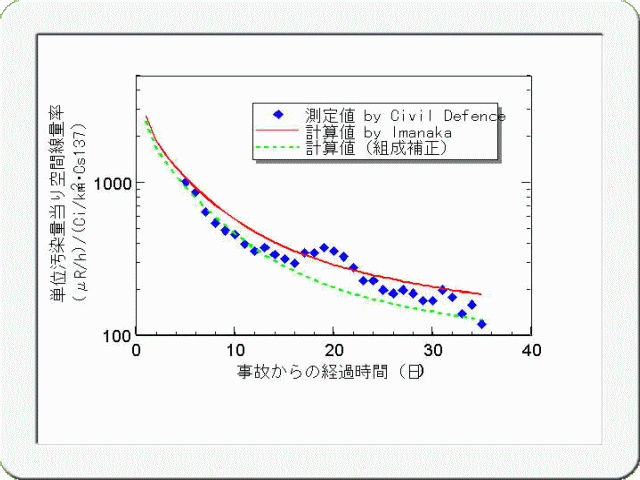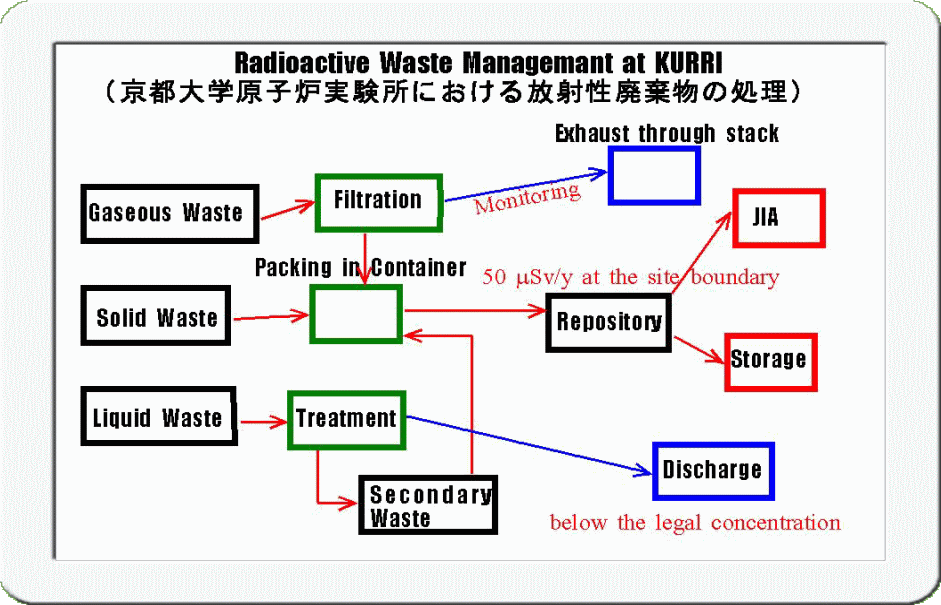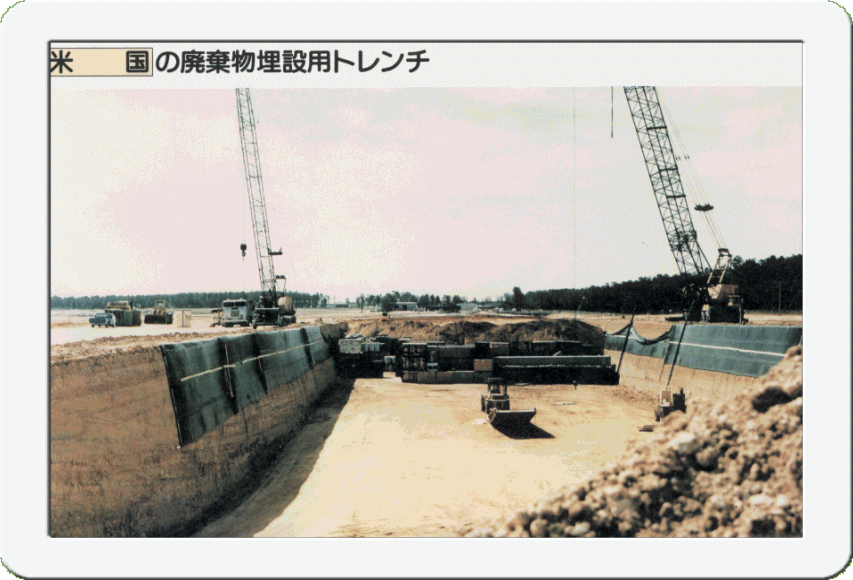分野研究現況
放射性廃棄物管理にはその特殊性から放射線安全性に関する十分な配慮が必要とされ、このため、放射性廃棄物処理・処分にともなう種々の問題点について工学的に研究を行っている。現在の中心的なテーマとして、放射性廃液処理に関して、塩分濃度が極めて高い蒸発濃縮液の脱水・安定化、エネルギー消費が少なく二次廃棄物発生量が少ない膜分離処理法の開発の研究を行っている。また、放射性廃棄物処分場や放射性フォールアウトの放射性核種の移行による影響の評価を行うため、セシウム、沃素、鉛等の核種について気温、降雨等の気象要因や土壌水分の変動と、地表、通気層、帯水層にわたる核種の移動挙動とのメカニズムを解明するためのカラム実験と、実環境中での核種移動を調査するフィールド実験を行っている。
放射性廃棄物管理に関する工学的研究
環境中放射能モニタリングと被曝線量評価に関する研究
原 子力施設から環境中に放出される放射能について、低レベル放射能の測定法を開発するとともに、環境中における放射能濃度を短期的・長期的に観測し、原子力運転の平常運転がもたらしている環境影響を明らかにする。具体的には、Ge半導体測定器による低レベルγ線分析法の開発、携帯型スペクトロメーターによる野外測定法の開発、原子力施設周辺の環境モニタリング、およびそれらのデータに基づく被曝線量評価などの課題に取り組む。
原子力施設大規模事故にともなう放射能汚染と災害評価に関する研究
原発等の原子力施設において大規模な放射能放出を伴う事故が発生した場合の影響を、 さまざまな放射能放出モード、気象条件下でシミュレーションし、周辺地域での放射能汚染や被曝線量の評価を行う。 また、旧ソ連チェルノブイリ原発事故や米国スリーマイル島原発事故など、実際に大規模な放射能放出を伴った原子力施設事故について、文献データの収集や独自の測定などを基に放射能汚染の解析を行い、災害規模の評価を試みる。