![]() 原子力安全問題ゼミ
原子力安全問題ゼミ
原子力安全研究グループが主催する非定期的な公開勉強会です。専門家、非専門家を問わず、原子力の安全問題に関心を抱く方々の参加を歓迎しています。
<最近の安全ゼミ>
<2015年2月27日 第111回 原子力安全問題ゼミ>
○伊方原発訴訟の頃 川野眞治(原子力安全研究グループ)
○原子力廃絶までの道程 小出裕章(京都大学原子炉実験所)
<2011年3月18日 第110回 原子力安全問題ゼミ>
○福島原発事故の現状について 小出裕章(京都大学原子炉実験所)
○スリーマイル島原発2号炉事故の概要 海老沢 徹(原子力安全研究グループ)
○
チェルノブイリ原発事故の概要 今中哲二(京都大学原子炉実験所)
○
Punishing
legacy of nuclear bomb and atomic energy projects in
Ukraine(原爆開発と原子力利用がもたらしたウクライナへの天罰)
TYKHYY
Volodymyr(ウクライナ科学アカデミー)
○
チェルノブイリ原発職員のインタビューより 七澤 潔(NHK放送文化研究所)
○ プリピャチ市避難住民へのインタビューより 川野徳幸(広島大
平和科学研究センター)
○ 科研費研究によるチェルノブイリ汚染地域ナロージチ地区での住人健康調査 木村真三(労働安全衛生総合研究所)
○
チェルノブイリ裁判記録を翻訳して 平野進一郎(チェルノブイリ子ども基金)
![]() 2010年9月7日(Tondel講演会)電磁波過敏症、自然放射線の発がん影響問題
2010年9月7日(Tondel講演会)電磁波過敏症、自然放射線の発がん影響問題
![]() Lecture-1: Electromagnetic hypersensitivity - state of the art and the legal situation in Sweden
Lecture-1: Electromagnetic hypersensitivity - state of the art and the legal situation in Sweden
![]() Comment: EHS Studies in Japan. 荻野晃也
Comment: EHS Studies in Japan. 荻野晃也
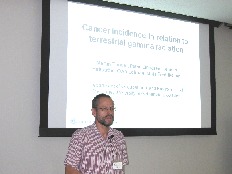
![]() Lecture-2: Cancer incidence in relation to terrestrial gamma radiation
in two Swedish counties
Lecture-2: Cancer incidence in relation to terrestrial gamma radiation
in two Swedish counties
(報告内容は、現在論文として投稿中のため、採否の結果がはっきりするまで割愛)
![]() Comment: Terrestrial Radiation and Cancer Mortality in Japan. 今中哲二
Comment: Terrestrial Radiation and Cancer Mortality in Japan. 今中哲二
![]() 2010年4月26日(第109回) 広島・長崎65年 被爆体験を聴く
2010年4月26日(第109回) 広島・長崎65年 被爆体験を聴く
![]() 65年前を振り返る 葉佐井 博巳
65年前を振り返る 葉佐井 博巳

![]() 被爆者として、そして科学者として 沢田 昭二
被爆者として、そして科学者として 沢田 昭二
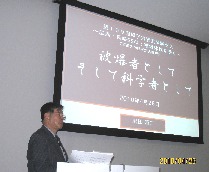
![]() 私の被爆体験から 沢田昭二
私の被爆体験から 沢田昭二
![]() 「核抑止を超えて」 湯川・朝永宣言(1975)
「核抑止を超えて」 湯川・朝永宣言(1975)
![]() 2009年10月26日(第108回) 地球温暖化と二酸化炭素
2009年10月26日(第108回) 地球温暖化と二酸化炭素
![]() 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告と温暖化二酸化炭素説の問題点 小出 裕章
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告と温暖化二酸化炭素説の問題点 小出 裕章
![]() 地球温暖化はどこまで二酸化炭素で説明できるか? 渡辺 宏
地球温暖化はどこまで二酸化炭素で説明できるか? 渡辺 宏
![]() 2009年8月7日(第107回) ナロジチ再生・菜の花プロジェクト
2009年8月7日(第107回) ナロジチ再生・菜の花プロジェクト
![]() 菜の花プロジェクトの経緯と概要 戸村 京子
菜の花プロジェクトの経緯と概要 戸村 京子

![]() The Consequences of Chernobyl Accident in the Agriculture of Zhytomyr region
and counter-measures against them Mykola Didukh
The Consequences of Chernobyl Accident in the Agriculture of Zhytomyr region
and counter-measures against them Mykola Didukh

![]() 2009年3月6日(第106回) 医療ひばくのリスク
2009年3月6日(第106回) 医療ひばくのリスク
![]() 低レベル被ばく影響に関する最近の報告より 今中 哲二
低レベル被ばく影響に関する最近の報告より 今中 哲二
![]() 医療ひばくのリスク 崎山 比佐子
医療ひばくのリスク 崎山 比佐子

![]() コメント1:医療従事者の被ばく 木村 真三
コメント1:医療従事者の被ばく 木村 真三
![]() コメント2:原発労働者の被ばく 渡辺 美紀子
コメント2:原発労働者の被ばく 渡辺 美紀子
![]() 2008年7月22日(第105回) 中越沖地震と原発耐震設計
2008年7月22日(第105回) 中越沖地震と原発耐震設計
![]() 柏崎刈羽原発とその地震被害の概要 小出 裕章
柏崎刈羽原発とその地震被害の概要 小出 裕章
![]() 中越沖地震が明らかにした原発耐震設計の問題点 正脇 謙次
中越沖地震が明らかにした原発耐震設計の問題点 正脇 謙次
![]() コメント:伊方原発訴訟と地震問題 荻野 晃也
コメント:伊方原発訴訟と地震問題 荻野 晃也
![]() 2007年6月28日(第104回)
2007年6月28日(第104回)
![]() Malignancies in Sweden after the Chernobyl Accident in 1986 Martin Todel (Linkoping Univ, Sweden)
Malignancies in Sweden after the Chernobyl Accident in 1986 Martin Todel (Linkoping Univ, Sweden)
![]() チェルノブイリからの放射能汚染によりスウェーデンでガンが増えている? 今中哲二
チェルノブイリからの放射能汚染によりスウェーデンでガンが増えている? 今中哲二
![]() 2007年5月11日(第103回) BWR臨界事故と能登地震:
2007年5月11日(第103回) BWR臨界事故と能登地震:
![]() BWR臨界事故と日本の原子力安全文化 小林圭二
BWR臨界事故と日本の原子力安全文化 小林圭二
![]() 志賀原発裁判と地震問題 岩淵正明
志賀原発裁判と地震問題 岩淵正明
![]() 島根原発と断層問題 芦原康江
島根原発と断層問題 芦原康江
![]() 2006年4月14日(第102回) チェルノブイリ事故20年:
2006年4月14日(第102回) チェルノブイリ事故20年:
![]() 事故の概要 今中哲二
事故の概要 今中哲二
![]() チェルノブイリ:科学技術文明への警告 ユーリー・シチェルバク
チェルノブイリ:科学技術文明への警告 ユーリー・シチェルバク
![]() 被災者の現状とその社会的問題 ボロジーミル・ティーヒー
被災者の現状とその社会的問題 ボロジーミル・ティーヒー
![]() 2005年6月10日(第101回)
2005年6月10日(第101回)
![]() 中性子とともに36年:市民と「アカデミズム」のはざまで 川野眞治
中性子とともに36年:市民と「アカデミズム」のはざまで 川野眞治
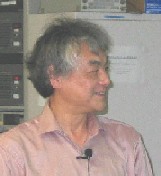
![]() 原発の重大事故を顧みて 正脇謙次
原発の重大事故を顧みて 正脇謙次
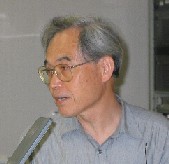
2005年3月22日(第100回):高速増殖炉「もんじゅ」−過去・現在・未来− 小林圭二
![]() 2004年12月15日(第99回) :低線量被曝リスクの諸問題
2004年12月15日(第99回) :低線量被曝リスクの諸問題
![]() 1.
ECRR報告における新しい低線量被曝評価の考え方
山内知也 (ECRR2003翻訳委員会)
1.
ECRR報告における新しい低線量被曝評価の考え方
山内知也 (ECRR2003翻訳委員会)
![]() ECRR資料:Executive
Summary
ECRR資料:Executive
Summary

![]() 2.低線量被曝リスク評価に関する話題紹介と問題整理
今中哲二
2.低線量被曝リスク評価に関する話題紹介と問題整理
今中哲二
![]() たまたまキエフにいました
たまたまキエフにいました

![]() 3.
フランス下請け労働者の被曝リスク計算例 桜井醇児
3.
フランス下請け労働者の被曝リスク計算例 桜井醇児

![]() 4.
コメント 小出裕章
4.
コメント 小出裕章
![]() α線内部被曝線量の評価方法についてのメモ
α線内部被曝線量の評価方法についてのメモ
![]() 劣化ウラン兵器と核サイクル
劣化ウラン兵器と核サイクル
![]() マンハッタン計画労働者の肺ガン
マンハッタン計画労働者の肺ガン
![]() 2004年10月7日(第98回) :美浜3号機復水配管破断事故
2004年10月7日(第98回) :美浜3号機復水配管破断事故
![]() 1.
事故経過とその全体像 小出 裕章
1.
事故経過とその全体像 小出 裕章
パワーポイントプレゼンテーション(6.8Mb)
![]() 2.
熱水力学条件の推移とプラントパラメータの変化-もう一つのシナリオ 海老澤徹
2.
熱水力学条件の推移とプラントパラメータの変化-もう一つのシナリオ 海老澤徹

![]() 3.
減肉現象とは何か-材料学からのコメント 正脇謙二 (京大工)
3.
減肉現象とは何か-材料学からのコメント 正脇謙二 (京大工)
![]() 4.
原発管理指針を考える-避けられなかった配管破断-
小山英之 (美浜の会)
4.
原発管理指針を考える-避けられなかった配管破断-
小山英之 (美浜の会)

![]() 2004年6月9日(第97回)
2004年6月9日(第97回)
コメント 内包されている六ヶ所再処理の危険性について考える 平野良一2004年3月17日(第96回) 日本の再処理は何処へ行く 古川路明
表1 図1 図2 図3 図4
![]() 2003年12月12日(第95回) 原発震災
2003年12月12日(第95回) 原発震災

原発の耐震設計技術指針と地震波 正脇謙次

安全審査における地震問題・・・伊方訴訟の経験から・・・ 荻野晃也


ジャドゥゴダ関連: 汚染測定報告
「レモン味の蟻」 「巨大なモンスター」
人形峠関連: 「意見書」
原子力と核を巡る動き: 「朝鮮の核問題」
![]() 2003年5月16日(第93回)
2003年5月16日(第93回)
原子力から始まって反原発に至る 小林圭二

退職して考える45年間の出来事:反原発・電磁波問題を中心として 荻野晃也

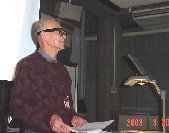
2003年2月25日(第91回) Assessment of Chernobyl Cancer in Belarus, MALKO Mikhail
Malko講演会の概要とコメント 今中哲二
![]() 2002年10月11日(第89回) JCO臨界事故:3年後に見えてきたこと 藤野 聡
2002年10月11日(第89回) JCO臨界事故:3年後に見えてきたこと 藤野 聡
![]() 2002年7月5日(第88回) 中性子と原子力 海老澤 徹
2002年7月5日(第88回) 中性子と原子力 海老澤 徹
![]() 2002年4月30日(第87回) 浜岡1号炉事故
2002年4月30日(第87回) 浜岡1号炉事故
3 浜岡1号機配管破断事故における原子炉の安全問題 海老澤徹
4 Brunsbuttel原発の水素爆発による配管破断事故について 安藤多恵子
![]() 2001年12月22日(第85回) 高レベル放射性廃棄物の地層処分
藤村 陽
2001年12月22日(第85回) 高レベル放射性廃棄物の地層処分
藤村 陽
(NetscapeNavigatorは文字化けするかも知れません。InternetExplorerの方をお勧めします。)
![]() 2001年10月23日(第84回) 風力発電の現状と問題点
石田 博
2001年10月23日(第84回) 風力発電の現状と問題点
石田 博
![]() 2001年8月9日(第83回) 地震と原発
2001年8月9日(第83回) 地震と原発
![]() 2001年6月1日(第82回) 核燃料輸送 ―そこから見えることー 尾崎充彦
2001年6月1日(第82回) 核燃料輸送 ―そこから見えることー 尾崎充彦
![]() 2001年3月16日(第81回) 激動の台湾原発事情
2001年3月16日(第81回) 激動の台湾原発事情
1 原子力発電所の安全評価と台湾への適用 小出裕章
2 台湾の原子力開発、過去、現在、未来
小村浩夫
資料:原発が直面する一大困難:核廃棄物 小村浩夫(2000.8.17台湾大学講演レジュメ)
![]() 2000年12月12日(第80回) JCO事故の総括的検討
2000年12月12日(第80回) JCO事故の総括的検討
1 JCO臨界事故とその背景にあるもの 古川路明
- 申請書類を見直す −
2 漏洩中性子の輸送計算
今中哲二
![]() 2000年9月27日(第79回) ウラン、トリウムなど天然放射能による被曝
2000年9月27日(第79回) ウラン、トリウムなど天然放射能による被曝
1 人形峠ウラン鉱山などの汚染と課題 小出 裕章
2 東郷町方面地区のウラン残土撤去運動 土井 淑平
3 堺臨海処分場のチタン汚泥 末田 一秀
4 堺におけるチタン汚泥問題 北 就一
5 神戸市北区富士チタン工場に関連する酸化チタン産廃 海老沢 徹
![]() 1999年12月27日(第77回) 今年の原子力安全問題
1999年12月27日(第77回) 今年の原子力安全問題
1.原電敦賀2号炉事故
事故の概要 久米三四郎
2.JCO臨界事故
![]() 1999年11月1日(第76回)JCO東海の臨界事故について
1999年11月1日(第76回)JCO東海の臨界事故について
中性子線量と発生出力 今中哲二
被曝と放射能汚染問題 小出裕章
原発の長期運転に伴う材料劣化の危険性 正脇謙次(京大工学部)
寿命延長と安全問題 海老沢徹(京大原子炉)
![]() 1999年2月17日(第73回)中地重晴「産廃処分場の現状から原発解体廃棄物による環境汚染問題を考える」
1999年2月17日(第73回)中地重晴「産廃処分場の現状から原発解体廃棄物による環境汚染問題を考える」
![]() 1998年12月22日(第72回) 槌田敦「炭酸ガスによる地球温暖化説を検討する」
1998年12月22日(第72回) 槌田敦「炭酸ガスによる地球温暖化説を検討する」
![]() 1998年10月6日(第71回) 淡川典子「原発をめぐる法的諸問題」
1998年10月6日(第71回) 淡川典子「原発をめぐる法的諸問題」
![]() 1998年5月13日(第70回) 海老沢徹「原発の老朽化問題と最近の安全問題」
1998年5月13日(第70回) 海老沢徹「原発の老朽化問題と最近の安全問題」